
HSS型HSPさんが抱えるストレスについて知りたい!

ナイスな視点だね!
くわしく解説していくね!
前半では、HSS型HSPさんが抱える矛盾について解説します。
後半では、HSS型HSPさんの心を軽くする考え方について紹介していきますよ!
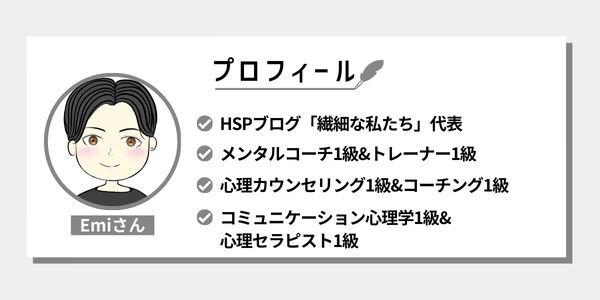

刺激を求めるのに、すぐ疲れるストレスの正体とは?
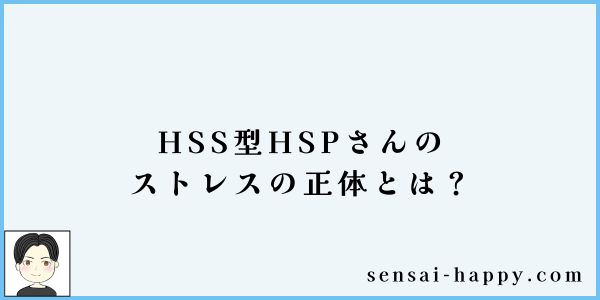
HSS型HSPさんは「刺激を求める性格」と「刺激に敏感な気質」の両方を持っているタイプ。
この2つは一見矛盾しているようで、心の中で常に引っ張り合ってしまう特徴があります。
例えば「旅行に行きたい!」と思っても、現地に着いたら人混みや音に疲れてしまうことがあるんです。

行動したいのに疲れる、この葛藤こそがHSS型HSPさんのストレスの根本にあるといわれています。
実際、心理学者アーロン博士の研究によれば、HSPさんの中でもHSS型の人は“感情的な揺れ”が特に大きい傾向があるとされています。
この感情のブレは、自律神経を疲れさせ、結果的に「動いたあとに急に落ち込む」状態を招きやすくなるんです。
さらに、社会の期待に応えようと無理をしすぎると、「なんでこんなに疲れるんだろう…」と自己否定につながってしまいます。

でもこれはあなたの性格が弱いわけではなく、脳の働き方の違いによる“反応”なんだ
だからこそ、
- 「疲れたら休む」
- 「予定を詰めすぎない」
といった刺激量のコントロールが大切になります。
心と体のバランスを保つために、あなたに合った「行動と休息のリズム」を探していくことが回復への第一歩なんです。
HSS型HSPさんが抱える矛盾とは?
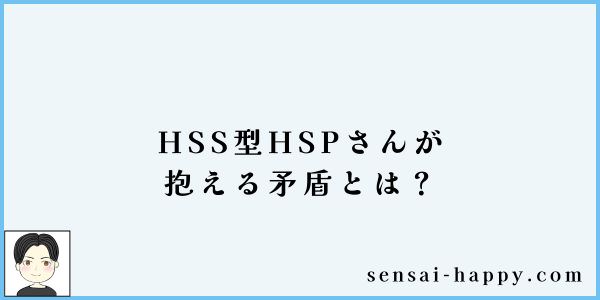
HSS型HSPさんは「新しいことに挑戦したい!」という欲求と、「刺激が多いと疲れてしまう…」という繊細さの両方を抱えています。
この矛盾する2つの性質が、心の中で常に綱引きをしているような状態を生み出しているんです。
例えば、人と会うのが好きなのに、集まりの後にぐったりしてしまったり、「楽しそう」と思って飛び込んだことにすぐに疲れてしまうことがあります。

これは「刺激探求傾向(HSS)」と「過敏な神経系(HSP)」が共存しているからなんです。
アーロン博士の研究でも、HSS型HSPさんは“内向的な冒険家”とも呼ばれ、強い葛藤を抱えやすいとされています。
つまり、行動を起こしてもすぐに心が悲鳴をあげやすく、疲れやすい一方で、じっとしていると逆にイライラしてしまうこともあるんです。
この矛盾を「変だから」と思う必要はありません。

あなたの脳の仕組みがそうなっているだけなんだ
だからこそ、「ワクワク」と「安心」の両方を少しずつ満たす暮らし方を意識すると、気持ちが安定しやすくなります。
予定を詰めすぎず、休息を織り込んだスケジュールを組むことが、HSS型HSPさんにとって大切なんです。
矛盾があるからこそ、そのバランスをとることで、あなたの個性が輝くようになりますよ◯
ストレスで“燃え尽きる”前にできること3選
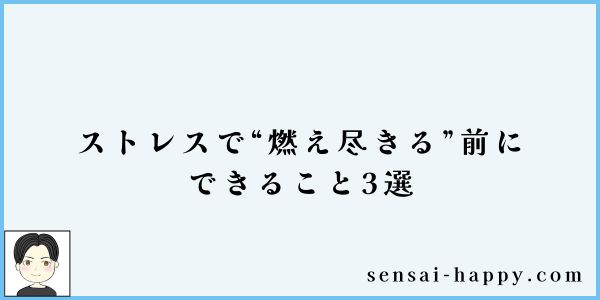
ストレスで“燃え尽きる”前にできること3選について解説します。
- スケジュールに“余白”をつくる
- 刺激のあとに“回復ルーティン”をする
- 「今どんな気分?」を確認する時間を持つ
1つずつ見ていきましょう。
1.スケジュールに“余白”をつくる
HSS型HSPさんは「やりたい」と感じる行動力がある反面、心のエネルギーがすぐに減ってしまいやすいんです。
予定をぎっしり詰めてしまうと、どこかでパンクしてしまうことがあります。
だからこそ、意識的に“休む日”や“何もしない時間”をつくってください。

例えば、1日の中に10分でも「刺激ゼロの時間」を設けるだけで、回復力が高まるという研究もあります。
特に、外出予定の翌日は、意図的に「空白時間」をとると気持ちが安定しやすくなるんです。
予定に余白を入れることは、さぼりではなく「繊細なあなたに合った働き方」に。
結果的に行動の質も上がるので、仕事や人間関係のパフォーマンスも保ちやすくなります。

ストレスが溜まりきる前に「調整する力」が、HSS型HSPさんにとって重要なんだ!
まずは“予定の入れ方”から、あなたの心を守ることを意識してみてください。
2.刺激のあとに“回復ルーティン”をする
HSS型HSPさんは、楽しい時間を過ごしても、あとからぐったりしてしまうことがあります。
これは神経系が人一倍反応してしまうからで、特に社交や冒険の後は「反動疲労」が起こりやすいんです。
そのため、刺激を受けた後に“回復するためのルーティン”を持つことが大切なんですよ◯
例えば、
- 深呼吸
- ぬるめの入浴
- 自然音のBGM
など、神経をクールダウンさせる時間を決めておくと効果的に◯
ハーバード大学の研究では、呼吸瞑想を行うことで自律神経の回復が早まると報告されています(Harvard Health Publishing, 2019)。
一度習慣にしてしまえば、「疲れたな」と思う前にケアができるようになるんです。

あなたの心と体に合った“お守りのような行動”を、今から見つけておくことが大切ですね◯

回復までがワンセット、という意識がHSS型HSPさんには必要なんだよ!
3.「今どんな気分?」を確認する時間を持つ
HSS型HSPさんは、人や状況に敏感で、無意識に気を使いすぎてしまうことがあるんです。
その結果、知らないうちに心が限界を超えていることもあります。
だからこそ、1日1回
- 「今どんな気持ち?」
- 「疲れていない?」
と、自分の感情に声をかけてあげてください。
感情にラベルを貼ることで、ストレス反応を抑える効果があるという心理学の研究もあります(Lieberman et al., 2007)。
例えば、「ちょっと不安かも」「気を張りすぎたな」と言葉にするだけで、感情は落ち着きやすくなるんです。

あなたの感情を見てあげることは、誰かに頼るのと同じくらいの癒し効果があります。
「疲れてない」と無理をするより、「疲れた」と言える強さが、あなたを守ってくれるんです。
日記やアプリでの感情記録もおすすめ◯

「心のチェックイン」を習慣化すると、燃え尽きる前に気づけるようになるんだよ!
ストレスを回復させる具体的行動10選
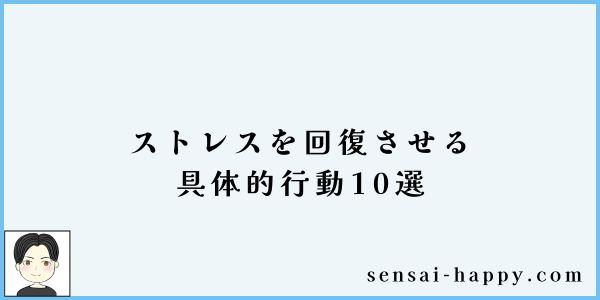
ストレスを回復させる具体的行動10選について解説します。
- 静かな場所でのひとり時間
- 感情を書き出すジャーナリング
- 五感を癒すリラクゼーション
- 1人だけの冒険を取り入れる
- ゆるい予定だけを入れる日
- 頭の中を空っぽにする時間
- 小さな達成感を意識的に得る
- 優しい人間関係
- バランスをとる
- 自分だけのストレス対策リスト
ゆっくり見ていきましょう。
1.静かな場所でのひとり時間
HSS型HSPさんは、外の刺激を好む反面、とても疲れやすい特性があります。
そのため、活動の後には、誰にも邪魔されない「ひとり時間」を持つことが必要なんです。
たとえば自然の中を散歩したり、静かなカフェで本を読んだりするのもおすすめ◯

こうした時間は、脳の過活動を落ち着かせる効果があるといわれています。
特に前頭前野の過剰な働きを鎮めることで、感情のリセットが促されるんです。
米国心理学会によると、「沈黙の時間」はストレス低減に役立つと報告されています。
意識して予定に“空白”を入れることが、あなたの心を守る鍵に◯

周囲に気を遣わずにいられる空間は、エネルギーを回復させる場所でもあるんだ
「何もしない時間」をあえてつくることで、次の行動にも前向きになれるんです。
日々の中に静けさを取り入れることで、HSS型HSPさんは本来の自分に戻れますね!
2.感情を書き出すジャーナリング
HSS型HSPさんは刺激に敏感なぶん、感情の整理が追いつかないことがあります。
そういう時は、紙に思ったことを自由に書く「ジャーナリング」がおすすめに◯
書くことで、脳の中の“もやもや”が外に出て、気持ちが落ち着きやすくなるんです。

ペンシルバニア州立大学の研究でも、感情の言語化は不安の軽減に効果があると示されています。
たとえば、「今日は疲れた。でも少し楽しかった」など短くても効果がありますよ。
頭の中でぐるぐる考えるより、紙に出すだけで脳の負担は軽くなるんです。
ネガティブな気持ちも否定せずに書くことで、自己理解が深まりやすくなります。

感情を整理することは、自分をケアする第一歩になるんだ
慣れないうちは箇条書きでも十分◯
書くこと自体に意味があるんです。
日常に3分でも取り入れてみると、思った以上に心が軽くなります。
3.“五感”を癒すリラクゼーション
HSS型HSPさんは五感が敏感だからこそ、リラクゼーションの効果が高いんです。
たとえば
- アロマの香り
- 温かいお風呂
- ヒーリング音楽
などが効果的に◯
こうした刺激は、交感神経の過活動を抑え、副交感神経を優位にしてくれるんです。
これは「自律神経バランス理論」にもとづく科学的なリラックス法。

アロマセラピーでは、ラベンダーの香りがストレス緩和に有効だとする論文もあります。
“静かな快感”を与えることで、HSS型HSPさんの神経系は整いやすくなるんです。
自分の感覚を満たすことは、脳の「報酬系」にもポジティブに作用します。
- 視覚
- 聴覚
- 嗅覚
- 触覚
- 味覚
のうち、あなたが心地よいと感じるものを選んでくださいね◯

五感を満たすことは、エネルギーを内側からチャージする方法なんだ!
感覚的な疲れには、感覚的な癒しがとても効果的に◯
4.1人だけの冒険を取り入れる
HSS型HSPさんは冒険心がある一方で、人と一緒だと気疲れしやすいんです。
そのため、“ひとり旅”や“ひとりカフェ巡り”などの「1人での冒険」がおすすめ◯
これは刺激を求める欲求を満たしながら、他人に気を使わずに過ごせる方法なんです。

米国スタンフォード大学の研究でも、「1人の体験」は自己効力感の向上に役立つとされています。
自分で決めて、自分で動く体験は、自己肯定感にもつながるんです。
誰かと一緒に行くと気疲れしてしまう場所でも、1人なら自分のペースで動けます。
HSS型HSPさんにとって「自由でありながら安全」という状態が心を回復させるんです。

無理に社交的になる必要はなく、あなたの好奇心に寄り添うだけでいいんだ
新しいことを体験すること自体が、あなたの脳に新鮮な刺激を与えてくれるんです。
1人冒険は、繊細な心を守りながらも、内なる冒険心を満たす方法に◯
5.ゆるい予定だけを入れる日
HSS型HSPさんは、予定が詰まっていると気を張り続けてしまい、疲れやすいんです。
予定があるだけで、頭の中で先読みや準備が始まってしまうから。
そこで、「ゆるく過ごすだけの日」を意識的に作ることが回復につながります。

例えば「お昼に散歩だけ」など、自分にプレッシャーがかからない予定を入れてください。
心理学では「決定疲労」という概念があり、選択の多さがストレスになるとされています。
あらかじめ“何もしない時間”を予定に入れることで、罪悪感が薄まりやすくなるんです。
これは脳科学でも「休息の予期」は実際の休息と同様に脳を癒すと言われています。

HSS型HSPさんは、頑張り屋で刺激好きだからこそ、意識的な「ゆるみ」が必要なんだ
気分のままに過ごす1日は、翌日の回復力を高めてくれる大切なメンテナンス日なんです。
だからこそ、週に1日は「ゆるい日」を取り入れてほしいなと思います。
6.空っぽにする時間をもつ
HSS型HSPさんは、頭の中が常に動いていて、思考が止まりにくい傾向があります。
そのため、あえて「ぼーっとする時間」や「マインドフルネス瞑想」を取り入れるのが効果的に◯
これは脳の“デフォルト・モード・ネットワーク”を休ませることで、認知疲労を軽減するためなんです。

2011年の神経科学の研究でも、短時間の瞑想がストレスホルモンであるコルチゾールを減少させると示されています。
例えば、1分でも「呼吸だけに集中する」習慣を作るだけで、脳は回復に向かうんです。
何も考えない時間は、感情の波に飲まれそうなあなたを落ち着かせてくれます。
特にHSS型HSPさんは、外的にも内的にも刺激を多く受けるので、意図的な“空白”が大切なんです。

SNSや情報をシャットアウトし、ただ目を閉じる時間を作ってみてね
その小さな静けさが、心の余裕を少しずつ取り戻してくれますね。
「空っぽにする習慣」は、長く続けられる心の健康法なんですよ!
7.小さな達成感を意識的に得る
HSS型HSPさんは理想が高く、常に刺激を求める反面、達成できないと自己否定に陥りやすいんです。
だからこそ、「小さな達成」を日常に取り入れて自己肯定感を高めていくことが必要。
心理学では「成功体験の積み重ね」が自己効力感を育てることが知られています。
例えば、
- 「ベッドを整えた」
- 「5分だけ掃除した」
などで十分なんです。
脳は達成を感じるとドーパミンを放出し、幸福感や意欲が回復しやすくなります。
大きな挑戦でなくても、小さな“やり遂げた感”がストレス耐性を育ててくれるんです。

「毎日できる“ミニ目標”」を1つだけでも意識してみてください。
これは脳科学的にもモチベーション維持に効果があるとされています。
小さな積み重ねは、燃え尽き症候群の予防にもつながるんです。

無理なく「できた!」を感じる工夫が、あなたを前向きに保ってくれるんだ
8.優しい人間関係
HSS型HSPさんは共感力が高いため、人間関係の中で強い影響を受けやすいんです。
そのため、否定的な人や圧の強い人と接すると、すぐに消耗してしまいます。
だからこそ、「安心していられる人」とだけ過ごす時間をつくることが重要なんです。

心理学者カール・ロジャースも「無条件の受容」が心の回復を促すと提唱しています。
例えば、家族や信頼できる友人、ペットとの時間などが回復を早めてくれるんです。
優しい人間関係は、あなたの中の繊細さを守る“心の栄養”に◯
無理に人付き合いを増やすのではなく、「心が緩む人」に囲まれるようにしてくださいね。

SNSのやりとりでも、ポジティブな交流だけに絞るだけで違いが出るよ
あなたにとって安全な人間関係は、ストレスからの回復に欠かせない土台なんです。
やさしさに触れる時間は、あなたの心に「安心ホルモン」を与えてくれますよ◯
9.バランスをとる
HSS型HSPさんは「刺激を求めるのに疲れやすい」という二面性を持っています。
だからこそ、
- 「楽しい刺激(例:旅行、挑戦)」
- 「落ち着ける時間(例:休息、自然散歩)」
の両方が必要なんです。
このバランスが崩れると、脳がオーバーワーク状態になり、燃え尽きやすくなります。
ポジティブ心理学では「快感系」と「満足系」のバランスが幸福感に影響するとされています。

例えば、午前中に外出したら午後は家でゆったりするなど、1日の中でも工夫ができますよね。
どちらかに偏るとエネルギーが偏るので、意識的にバランスを取ってください。
「行動したら、癒す」このリズムを作ることが、長く快適に生きるコツに◯
HSS型HSPさんには、強さも弱さもあるからこそ、どちらも尊重することが大切なんです。

どちらかを否定せず、両方のあなたを肯定することが心の回復に繋がるんだ
バランスが取れた日々は、HSS型HSPさんの“本来の魅力”を引き出してくれます。
10.自分だけのストレス対策リスト
最後におすすめなのが、「あなただけのストレス対策リスト」を作っておくこと。
HSS型HSPさんは繊細で感情の波も大きいため、調子が悪いときには判断力が落ちやすくなるんです。
そんなときに、“あらかじめ決めておいた”対処法があると、すぐに実行に移せます◯

心理療法でも「コーピングリスト(対処行動の一覧)」を作ることで不安や抑うつが軽減することが知られています。
例えば、
- サウナに行く
- 友達と遊ぶ
- 小説を読む
などをリスト化しておくと便利です。
感情の波にのまれる前に“準備しておく”ことが、繊細な心を守る大切な鍵に◯
ストレス対策は万能なものではなく、あなたに合うものを選ぶことが大切なんです。

リストを作ることで、「何をしたらラクになれるか」が視覚的にもわかりやすくなるんだ
そして、「また辛くなっても大丈夫」と思える安心感が生まれます。
あなたの心を守る方法を、あなた自身が知っておくことが、一番の強みになりますね。
HSS型HSPの心を軽くする考え方

HSS型HSPの心を軽くする考え方について解説します。
- もっと頑張らなきゃと思っていませんか?
- 二面性のある自分を否定しないで
- 他人と比べるクセを手放しませんか?
- 感情に揺れやすい自分を責めない
- 自分に休む許可を出そう
1つずつ見ていきましょう。
1.もっと頑張らなきゃと思っていませんか?
HSS型HSPさんは、刺激を求める行動力と、繊細さを持ち合わせているタイプ。
そのため、行動したあとはすぐに疲れやすくなり、「こんなことで疲れるなんて…」と感じてしまうことも多いんです。
このような思考のクセは、自分を責める「無意識の自己否定」につながっていくんですよね。

心理学では「セルフトーク(自分への語りかけ)」がメンタルに影響することが知られています。
例えば「自分はまだまだ足りない」と繰り返すと、本当に自信を失いやすくなるんです。
逆に、「今のあなたは、十分がんばってる」と認めるだけで、心は少し軽くなります。
HSS型HSPさんは感受性が高いため、自分の言葉にも強く影響されやすいんです。

だからこそ、「まだまだ」より「ここまでできた」に意識を向けてみてね!
心がホッとする言葉を、自分に届けてあげることが第一歩ですね!
2.二面性のある自分を否定しないで
HSS型HSPさんは
- 「行動したいのに疲れやすい」
- 「人といたいのに1人になりたい」
という相反する気持ちを抱えやすいんです。
このような矛盾に苦しみ、「どっちつかずの自分はダメかも」と思ってしまう方も少なくありません。
でも実は、この“両方の気質を持っている”ことこそが、あなたの強み!

心理学では「自己受容」がストレスを減らし、レジリエンス(回復力)を高めるとされています。
例えば、外向的な日もあれば内向的な日もある、それはごく自然なことなんです。
「ブレている」のではなく、「幅がある」ことを認めてあげてくださいね◯
どちらの側面も、あなたという一人の人間にとって大切な要素なんです。

無理にどちらかに決めつけず、「今日はどちらの気分かな?」と優しく問いかけてみてね!
二面性を受け入れると、あなたの中に安心感が広がっていきます。
3.他人と比べるクセを手放しませんか?
HSS型HSPさんは周囲に敏感で、人の雰囲気や能力をよく察知できます。
その力は素晴らしいんですが、時に「自分は劣っている」と感じやすい原因にもなります。
SNSや職場などで他人の成果ばかりを目にすると、「自分には無理かも」と思ってしまいやすいんです。

でも実際には、見えているのは“相手の一部分”だけ
社会心理学の研究でも、比較対象が多いほど人は自己評価を下げる傾向にあるとされています(Festinger, 1954)。
あなたが「すごい」と思う人にも、見えない不安や迷いがあるんです。
大切なのは、「昨日のあなた」と比べてみること。

ほんの少しでも進んだ実感を持てると、自信が育っていくよ!
他人のペースではなく、あなた自身のリズムを信じてください。
4.感情に揺れやすい自分を責めない
HSS型HSPさんは、ちょっとした言葉や表情にも強く反応しやすいんです。
それによって気持ちが大きく揺れたり、一日中気分が沈んでしまうことも。
でも、それは「あなたに問題がある」のではなく、「感受性が高い」から。
実際に脳科学の研究では、HSPさんは共感に関わる脳の領域(島皮質など)が活性化しやすいことがわかっています(Acevedo et al., 2014)。

つまり、感情の動きが豊かで、人の痛みにも敏感でいられる能力を持っているんです。
この繊細さを「弱さ」ではなく、「やさしさの源」と捉えてみてください。
あなたが何かに動揺したときは、「それほど真剣に向き合ってる証拠」◯
感情を感じること自体は悪いことではなく、あなたの個性なんですよ。

責めるのではなく、「そんな風に感じる日もあるよね」と寄り添ってあげてね!
5.自分に休む許可を出そう
HSS型HSPさんは、周りを気にするあまり、自分の疲れに気づくのが遅れがち。
- 「まだ頑張れる」
- 「これくらい大丈夫」
と思って無理をしてしまうことも多いんです。
でも、限界を超える前に“自分の内側の声”を聞くことがとても大切◯
認知行動療法では、「身体反応(疲労・緊張)」に早めに気づくことがストレス予防につながるとされています。

例えば、頭痛や肩こり、集中力の低下などが出たら、それは休息のサインなんです。
「今は休むことが最優先」と思い切って立ち止まることが、長い目で見れば回復への近道に。
あなたが倒れてしまっては、大切なものも守れなくなってしまうからなんです。
休むことは、怠けではなく「あなたの心を整える時間」ですよ◯

あなた自身に「休んでいいよ」と声をかけてあげてね
刺激に振り回されず、満たされる習慣術3
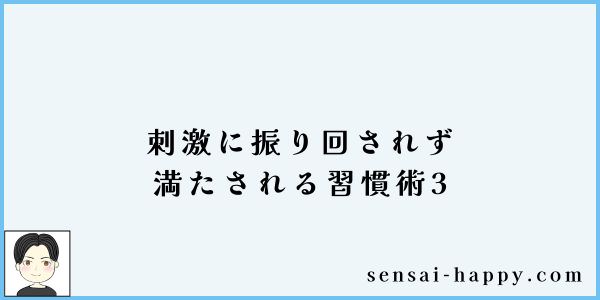
刺激に振り回されず、満たされる習慣術3つについて解説します。
- 朝の静かな時間に“内側の声”を聞く
- やらないことリストを作る
- 小さな“感動体験”を記録する
1つずつ見ていきましょう。
1.朝の静かな時間に“内側の声”を聞く
HSS型HSPさんは、外の刺激に敏感で、一日のはじまりから情報に巻き込まれやすい傾向があるんです。
だからこそ、朝いちばんに「静かな時間」を意識的に取ることが大切に◯
朝にスマホやニュースを見ず、5〜10分でも瞑想や深呼吸をするだけで、心が落ち着きやすくなります。
この習慣は、脳の“デフォルト・モード・ネットワーク”を整えることで、ストレスの予防にもつながるとされています(Tang et al., 2015)。
- 「今日はどんな気分か」
- 「何をしたら気分が満たされそうか」
と内面に問いかけてみてください。
外の刺激ではなく、内側の感覚をキャッチすることが、HSS型HSPさんの軸をつくるんです。
心の声に耳を傾けると、不思議と一日が穏やかに流れやすくなります。

朝の静けさは、あなたにとって大切な“充電時間”に。

まずは1日5分から、取り入れてみてね!
2.やらないことリストを作る
HSS型HSPさんは、好奇心が強く、ついついタスクを増やしがち。
たくさんのことに挑戦したくなる反面、気づいたら疲れ果てていることも多いんです。
そんなときにおすすめなのが「やらないことリスト」を作る習慣。

心理学では「意思決定の負荷」がストレスの大きな要因になることがわかっています。
「自分を疲れさせる行動」や「合わない人との付き合い」など、手放すべきことを明確にすることが回復への第一歩。
やらないことを決めることで、あなたの中に“余白”が生まれます。
その余白が、あなたらしい生き方の土台に◯

一度立ち止まり、手放すものを見直してみてね!
「やめる習慣」は、あなたを守る“やさしさ”なんです。
3.小さな“感動体験”を記録する
HSS型HSPさんは、日常の中の小さな出来事にも深く感動する力を持っているんです。
でも、刺激に振り回されてしまうと、その感動が流れてしまうこともあります。
そこで大切なのが、「感動したこと」を1日1つ書き留める習慣に◯
ポジティブ心理学の研究では、「日々の感謝を記録することで幸福感が高まる」ことがわかっています(Emmons & McCullough, 2003)。
例えば
- 「鳥の声が心地よかった」
- 「カフェで静かな時間が取れた」
など、小さなことでOK◯
それを記録するだけで、感性が“満たされる方向”に向いていくんです。
あなたの感性は、とても豊かで価値のあるもの。

日々の記録を通して、自分の感受性を肯定してあげてくださいね。

「感じる力」は、あなたの人生を彩るギフトなんだ!
HSPのよくある質問

HSPのよくある質問をまとめました。
- 辛い時にできる思考リセット術
- HSPはわがまま?
- プレッシャーに弱いのはどうして?
1つずつ見ていきましょう。
辛い時にできる思考リセット術
「辛い時にできる思考リセット術について教えてください」という相談。

4つ解説しているよ!

心の限界を感じた時の対処法についても5つ紹介していますよ!
HSPはわがまま?
「HSPはわがままですか?」という相談。

そんなことないよ!

伝え方によっては誤解を招くこともあるかもしれません..!
プレッシャーに弱いのはどうして?
「プレッシャーに弱いのはどうしてですか?」という相談。

生まれつきの特性だからだよ

“脳の情報処理の深さ”が関係しています◯
HSPの私・体験談

HSPの私・体験談を紹介します。
あなたの励みになったら嬉しいです。
二面生を持っていることを許す
刺激追求・刺激による疲れやすさ、この相反する2つの側面を同時に持っているという自分を許すことで、自身に優しくなれます。
HSPという概念を知る前は、なんで疲れやすいのかなと自分をマイナスに捉えることが多かったです。
しかし、理解を深めていくことで、それが当たり前であることを知りました。
人口の6%しか該当しないことなど、理解されづらいのが当然だと腑に落ちました。

だれかに理解してもらうことも大切ですが、自分自身が認めてあげることが何よりも大切です◯

今の自分にOKを出してあげてね!
















