
HSPさんがよく寝るのはどうして?

それは非HSPさんと比べて脳が活発に動いているからだよ!
前半では、HSPさんがよく寝る理由を3つ解説していきます。
後半では、寝ても疲れが取れない時のチェックポイントを3つ、科学的根拠をもとに紐解いていきますよ!
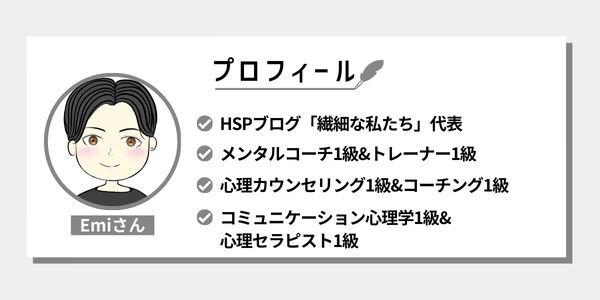

HSPがよく寝る理由3つ

HSPがよく寝る理由3つを解説します。
- 脳が常にフル回転している
- 感覚過多の“ノイズ”をリセットしている
- “外界との距離”をつくる大切な防衛手段
1つずつ見ていきましょう。
1.脳が常にフル回転している
HSPさんは、
- 人の表情
- 声のトーン
- 小さな環境の変化
まで、一度にたくさんの情報を処理しています。
そのため、見た目には何もしていなくても、脳の中ではずっと思考や感覚の処理が行われていて、“脳の疲れ”がたまりやすい傾向があります。
この脳疲労を回復させるには、十分な睡眠が必要不可欠なんです。
Aron博士の研究(1997)でも、「HSPさんは非HSPよりも脳の活動領域が広く、処理量が多いため、回復にもより長い時間を要する」と示されています。

HSPさんがよく寝るのは“怠け”ではなく“脳の防衛反応”なんですよ!

あなたが長く寝ることは、心と体を守るために自然なことなんだ!
2.感覚過多の“ノイズ”をリセットしている
HSPさんは、光・音・におい・人の気配など、普通なら気にならない刺激もすべて敏感に受け取る特徴があります。
こうした感覚過多は、脳だけでなく身体にも知らないうちに大きなストレスをかけているんです。
眠っている間、脳はその日受けた感覚情報を整理し、感情や記憶の“掃除”を行っているといわれています。
研究によると、HSPさんは「感覚の刺激処理に時間がかかるため、深い睡眠での整理プロセスがより重要」とされています(Jagiellowicz et al., 2011)。

そのため、たっぷり眠ることが心身のバランスを整えるカギなんです。

あなたがしっかり眠ることは、日中を安心して過ごすための準備なんだよ!
3.“外界との距離”をつくる大切な防衛手段
HSPさんは、他人の感情や場の空気を敏感に察知し、“自分以外のもの”に気を遣いすぎてしまう傾向があります。
一日中外の刺激を受けていると、知らず知らずのうちに“自分が消耗している”ことに気づけないまま疲れてしまうんです。
睡眠は、そうした外界との接触を一度断ち切り、“自分だけの安全な空間”に戻るための大切な行為でもあるんです。
心理学では「HSPさんは刺激遮断の時間を持たないと、自己の回復がうまくいかなくなる」と報告されています(Aron & Aron, 1997)。
周りに合わせて睡眠時間を削る必要はありません。

眠る時間はただの休息ではなく、あなたにとって“安心を取り戻す時間”なんです。

あなたの感性を守る手段として、安心して眠って大丈夫!
HSPが「ずっと眠い」と感じる3つの理由

HSPが「ずっと眠い」と感じる3つの理由を解説します。
- 日中の刺激で脳が疲れている
- 睡眠中に感情や情報を“深く整理”している
- 限界を超えていることが多い
ゆっくり見ていきましょう。
1.日中の刺激で脳が疲れている
HSPさんは、人や環境のわずかな変化にも反応してしまい、脳が休まる時間が少ない傾向に。
たとえ一見のんびり過ごしていても、頭の中では情報処理が続き、脳がオーバーワーク状態になってしまいやすいんです。
この“脳の疲れ”が慢性的になると、日中も眠気が抜けなくなることがあります。
Aron博士の研究(1997)でも、HSPさんの脳は通常よりも広範囲にわたって刺激に反応しやすいと報告されています。

刺激を受けやすい体質そのものが、眠気につながる要因なんです。
2.睡眠中に情報を“深く整理”している
HSPさんは、日々の出来事に強く心を動かされ、感情の処理に多くのエネルギーを使っているんです。
そのため、睡眠時間が十分でも、処理すべき“感情のデータ”が多くて脳がまだ休みきれていないことがあります。
特にレム睡眠中には感情や記憶の整理が行われるため、HSPさんは長めの睡眠が必要になることが多いんですよね。
心理学では「感情処理に過敏な人ほど、深い眠りによる修復が重要である」とされています(Walker, 2009)。

“まだ眠い”と感じるのは、感情をしっかり消化しようとしている脳からのサインなんです。

あなたがたくさん眠るのは、心を守る自然な行動なんだよ!
3.限界を超えていることが多い
HSPさんは、他人や周囲を優先しがちな性質から、自分の疲れに気づくのが遅れやすい傾向があります。
そのため、気づかないうちに“疲れの貯金”がたまっている状態になってしまうこともあるんです。
ある日、身体が急に重く感じたり、寝ても寝ても眠いと感じたりするのは、身体が「もう限界」と知らせているサインなんですよ。
Aron博士によると、HSPさんはストレスを表に出さず、「静かに疲れが蓄積していくタイプ」だとされています。

だからこそ、“ずっと眠い”と感じるときは、あなたの体と心が本気で休息を求めている証拠なんです。

無理せず、こまめに休むことがHSPさんには大切だよ!
寝ても疲れが取れない時のチェックポイント3
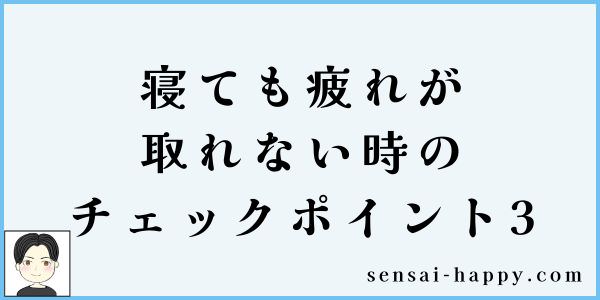
寝ても疲れが取れない時のチェックポイント3つを解説します。
- 睡眠の“質”が下がっていないか
- 日中の“感覚刺激”が多すぎる
- 心の疲れが溜まりすぎていないか
1つずつ解説します。
1.睡眠の“質”が下がっていないか
HSPさんは刺激に敏感なため、
- 音
- 光
- 温度などの微細な変化
でも睡眠の質が下がりやすいです。
たとえ長時間眠っていても、眠りが浅くなっていると疲労回復の効果が十分に得られません。
例えば、寝室に小さな音が鳴っていたり、照明の光が目に入ったまま眠っていないか確認してみてください。
また、寝る前のスマホやカフェイン摂取なども脳を覚醒させ、深い眠りを妨げる要因になります。
Walker(2017)の研究では、睡眠の長さよりも“質”が健康に直結すると指摘されています。

あなたが「よく寝てるのに疲れる」と感じるときは、眠りの深さに目を向けてみてくださいね。

暗い部屋で寝ることをおすすめするよ
2.日中の“感覚刺激”が多すぎる
HSPさんは、日中に受ける音・光・会話・人間関係など、あらゆる刺激を細かく受け取って処理しているんです。
そのため、眠っている間にもその“情報の処理”が続いてしまい、脳が完全に休まりきらない状態になっていることがあります。
あなたが「休んだはずなのに、まだだるい」と感じるときは、日中の過ごし方を見直す必要があるかもしれません。
例えば、
- 移動中の音楽をやめて静かに過ごす
- SNSを見る時間を減らす
など、意識的に“感覚の入力”を減らしてみてください。
Aron博士(1997)の研究では、「HSPさんは刺激の処理に多くの脳リソースを使う」と報告されています。

眠るだけでは回復しきれない場合もあるんです。

“日中の静けさ”が、夜の休息の質を高めてくれるんだ!
3.心の疲れが溜まりすぎていないか
HSPさんは、他人の感情や空気を敏感に察知しやすく、無意識のうちに“人間関係のストレス”を抱えてしまうことが多いです。
心の疲れは身体の疲れと違って見えづらいため、気づいたときには強い眠気や無気力として表れることがあります。
例えば、
- 「あの一言がずっと気になっている」
- 「なんとなく会いたくない人がいる」
と感じている場合は、心がSOSを出しているサインかもしれません。
心理学の研究でも、「HSPさんは共感力が高く、感情の疲労を他者より深く感じる」と指摘されています(Acevedo et al., 2014)。

眠っても取れない疲れは、心が「まだ片づけられていないよ」と教えてくれている状態なんです。

あなたの“心の荷物”にも、ぜひ耳を傾けてみてね!
「よく寝る=甘え」ではない理由3選
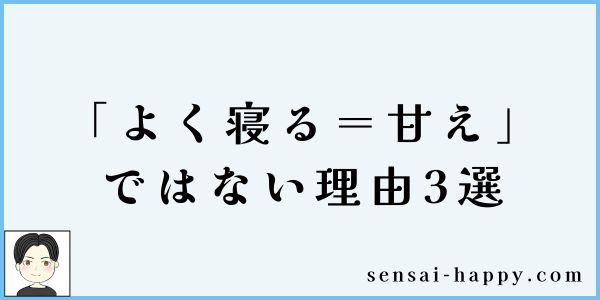
「よく寝る=甘え」ではない理由3選を紹介します。
- HSPの脳は休息に時間がかかる
- “感情とストレス”を整理する重要な時間
- 他人に合わせすぎて疲れてしまう
ゆっくり見ていきましょう。
1.HSPの脳は休息に時間がかかる
HSPさんは、まわりの小さな変化にも敏感に反応し、脳が常に情報を処理し続けています。
たとえあなたが「何もしていない」と感じていても、脳の中はフル稼働の状態が続いているんです。
そのため、非HSPの人と同じ時間では脳の疲労が取れず、長い睡眠が必要になることがあるんですよね!

これは甘えではなく、あなたの神経システムが“深い回復”を求めている証拠なんです。
Aron博士(1997)の研究でも、HSPさんは非HSPに比べて脳活動が高く、“回復に時間がかかる傾向”があると示されています。
長く眠ることは「弱さ」ではなく、「繊細な感性を守る行動」なんです。

あなたがよく眠るのは、本能的に自分を守っている証なんだ!
2.“感情とストレス”を整理する重要な時間
HSPさんは、感受性が高く、日常のちょっとした出来事にも深く心が動かされることが多いんです。
その感情はすぐに消えるものではなく、睡眠中に脳が整理し、少しずつ処理されていきます。
つまり、よく眠ることは感情の回復にとってとても大切なプロセスなんですよ◎
特にレム睡眠中には、記憶と感情の統合が行われ、ストレスの軽減に役立つことが研究でも示されています(Walker, 2009)。

あなたが「寝すぎかな」と思うほど眠るのは、それだけ感情を丁寧に扱っている証なんです。

甘えどころか、心の健康を守るための自然な防衛反応なんだよ
3.他人に合わせすぎて疲れてしまう
HSPさんは共感力が高く、人間関係で無意識に気をつかいすぎてしまう傾向があります。
その結果、自分では意識していなくても、“人といるだけで疲れてしまっている”状態になることがあるんです。
こうした「社会的な疲れ」は、目に見えづらく、周りから理解されにくい疲労の一つなんですよね。
Acevedoら(2014)の研究によると、HSPさんの脳は「他者の感情」に強く反応する領域が活性化するため、人間関係だけで脳が消耗することが確認されています。

その疲れを回復するには、十分な睡眠がもっとも効果的なんです。

あなたがよく眠るのは“甘え”ではなく、他人に寄り添いすぎた心のケアなんだ!
HSPが心地よく眠るための工夫3つ

HSPが心地よく眠るための工夫3つを紹介します。
- “感覚刺激”を最小限に整える
- 寝る前に情報のシャットダウン
- “こまめに回復する”意識
1つずつ見ていきましょう。
1.“感覚刺激”を最小限に整える
HSPさんは、音や光、肌の感触などわずかな環境の変化にも敏感に反応しやすいんです。
そのため、寝室の環境を整えることが、質の高い睡眠への第一歩になります。
例えば、
- 遮光カーテンで光を遮る
- 耳栓やホワイトノイズを使って音をやわらげる
- 肌ざわりのよいパジャマを選ぶ
など、五感への刺激をやさしく調整することが効果的です。
研究でも「睡眠環境の刺激が少ないほど、深いノンレム睡眠に入りやすくなる」と報告されています(Buysse et al., 2011)。

心地よい眠りは、“敏感な感覚”を安心させてあげることから始まるんです。

お気に入りのタオルを使うのもいいね!
2.寝る前に情報のシャットダウン
HSPさんは、SNSやニュース、人との会話などから得た情報を深く考え込んでしまいやすいんです。
そのまま眠ろうとすると、脳が活発なままでなかなか眠りのスイッチが入らなくなってしまいます。

寝る1時間前からスマホやテレビをオフにして、静かな時間をつくることがとても大切なんだ!
例えば、間接照明のもとで読書をしたり、ストレッチをしたりすることで、脳が安心して“休む準備”に入れるようになります。
Walker(2017)の研究でも、「睡眠前のブルーライト遮断はメラトニン分泌を促進し、入眠をスムーズにする」とされています。

あなたが安心して眠りにつくには、“頭を静かにする習慣”が必要なんです。
3.“こまめに回復する”意識
HSPさんは、日中に多くの刺激を受けているため、1日の終わりにはエネルギーがほとんど残っていない状態になりやすいです。
そのまま夜に倒れこむように眠ってしまうと、疲れすぎてかえって眠りが浅くなることもあるんですよ。
そこで、日中にも意識的に休憩を取る「こまめな回復」が大切になってきます。
例えば、
- 昼に5〜10分だけ目を閉じる
- 静かな音楽を聴く
- 香りを使ってリフレッシュする
など、少しずつ“疲れを軽減する習慣”を持ってみてください。
研究でも「睡眠の質は“日中のストレス負荷”によって左右される」と示されています(Morin et al., 2003)。

あなたが心地よく眠れるようになるには、夜だけでなく“昼間のケア”も必要なんです。

できるなら昼寝を推奨するよ!
朝起きた時に疲れが残る時の対策3
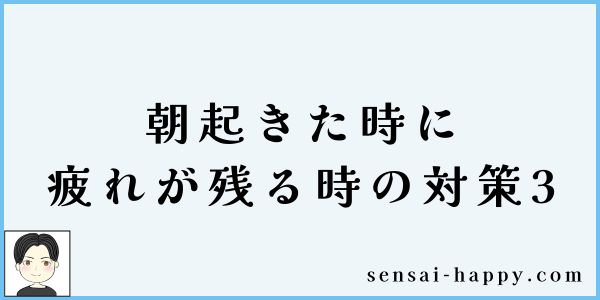
朝起きた時に疲れが残る時の対策3つを解説します。
- 就寝前のルーティンを“静かな時間”に
- 起きたあとすぐに“朝の光”を浴びる
- 起床後30分は“やさしいリズム”
ゆっくり見ていきましょう。
1.就寝前のルーティンを“静かな時間”に
HSPさんは就寝直前まで頭がフル回転していると、脳が休息モードに切り替わりにくいんです。
たとえば、寝る前にスマホを見たり、情報をたくさん入れてしまうと、眠っても脳が休まりきらないことがあります。
そこで効果的なのが、寝る1時間前から“刺激を減らす時間”を持つことなんです。
- 照明を暗めにする
- ハーブティーを飲む
- やさしい音楽を聴く
など、五感をリラックスさせる習慣をつくってみてください。
研究でも、夜の静けさが睡眠の深さに影響することが示されています(Walker, 2017)。

あなたの心と脳に「もう安心していいよ」と伝える時間が、翌朝の疲れを軽くするカギなんです。
2.起きたあとすぐに“朝の光”を浴びる
朝の疲れが残るときは、体内時計がうまくリセットされていない可能性があります。
HSPさんは特に、睡眠と覚醒の切り替えが繊細なので、「朝にしっかりスイッチを入れること」が重要なんです。
- カーテンを開けて自然光を浴びる
- 窓際で5分間深呼吸する
だけでも、脳が「朝だ」と認識しやすくなります。
光を浴びることで、セロトニンという“覚醒のホルモン”が分泌され、心身が目覚めやすくなるんです。
Chronobiology International誌の研究(2016)でも、「朝の光は睡眠の質と日中の疲労軽減に効果がある」とされています◎

つまり、朝の疲れには“夜”だけでなく、“朝の過ごし方”も大きく関係しているんです。

朝、起きたらすぐ陽の光を浴びるようにしているよ!
3.起床後30分は“やさしいリズム”
HSPさんは、朝起きた直後から激しい動きや音にさらされると、交感神経が急に高ぶってしまい、かえって疲れやすくなるんです。
だからこそ、朝の時間は“静かに目覚める”工夫が必要なんです。
例えば、
- 起きてすぐにカーテンを開ける
- 白湯を飲む
- 軽くストレッチをする
- 音楽をかける
など、心地よく五感を目覚めさせるルーティンがおすすめです。
こうした“スローな朝習慣”が、自律神経の安定をうながし、頭と身体のエンジンを自然にかけてくれるんです。
研究でも、特にHSPさんのように感受性の高い人は「刺激の強すぎない目覚め」が一日のパフォーマンスに影響することがわかっています(Greven et al., 2019)。

やさしい朝の時間が、その日の“疲れ残り”を軽くする力になるんです。

軽くストレッチするのは効果的だったよ!
HSPの朝活の相性と注意点3
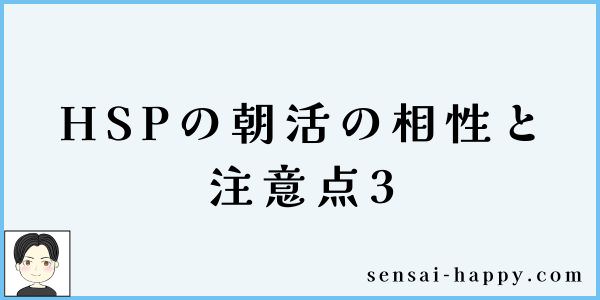
HSPの朝活の相性と注意点3つを紹介します。
- “朝の静けさ”と相性がいい
- やりすぎると“自己否定”に
- 感覚が静かに目覚める工夫
1つずつ解説します。
1.“朝の静けさ”と相性がいい
HSPさんは、静かな環境や落ち着いた空間で力を発揮しやすい気質を持っています。
早朝の時間帯は人が少なく、騒音や情報の刺激が少ないため、感覚が敏感なHSPさんにとってはとても過ごしやすいんです。
特に
- 読書
- 瞑想
- 軽い運動
など、自分と向き合う時間にはぴったりなんです。
朝は脳のリソースがクリアで、新しい情報を受け入れやすい時間帯でもあります。
心理学の研究でも、「静かな環境ではHSPさんの集中力や創造性が高まる」と示されています(Aron & Aron, 1997)。

つまり、朝活はHSPさんの“内なる力”を引き出しやすい時間なんです。

あなたのペースで使うことで、充実した一日を始められる武器になるんだ!
2.やりすぎると“自己否定”に
HSPさんはまじめでがんばり屋さんな傾向があり、「朝活をしなきゃ」と無理をしてしまうことがあります。
たとえば、SNSや本に影響されて、「毎朝5時に起きて成果を出す人」になろうとしてしまうと、かえって疲れて自己嫌悪に陥ってしまうこともあるんです。
朝活はあくまで“あなたの体調と心に合った範囲で行うもの”であってほしいなと思います。
心理学の観点でも、HSPさんは“できなかった自分”を責めやすい特性を持つとされています(Greven et al., 2019)。
だからこそ、
- 「今日はできた」
- 「昨日より5分早起きできた」
など、やさしい目線で振り返ることが大切なんです。

朝活は、自分を高める手段ですが、自分にやさしくなる時間にもしてほしいです◎

優しく、ちょっとずつ前進するイメージだよね!
3.感覚が静かに目覚める工夫
HSPさんは、
- 朝から強い光
- 大きな音
- 激しい運動
などに触れると、自律神経が過剰に反応してしまい、かえって疲れやすくなる傾向があります。
そのため、朝活を始める際には、“やさしく目覚めるためのステップ”がとても大切なんです。
- カーテンを少しずつ開けて自然光を取り込む
- やさしい音楽を流す(小鳥の声やピアノ音など)
- 白湯を飲む、香りを感じる(ラベンダーや柑橘系など)
- 簡単なストレッチで身体をゆるめる
こうした静かな刺激は、副交感神経をやさしく保ちながら覚醒をうながし、その後の活動を快適にしてくれます。
研究でも、「HSPさんの覚醒には急激な刺激よりも段階的な目覚めが効果的」と示されています(Acevedo et al., 2014)。

あなたの朝活は、“静けさ”を味方につけることがコツなんです。

やさしく目覚めるがコツだね!
HSPが朝活をやめた方がいいサイン3選
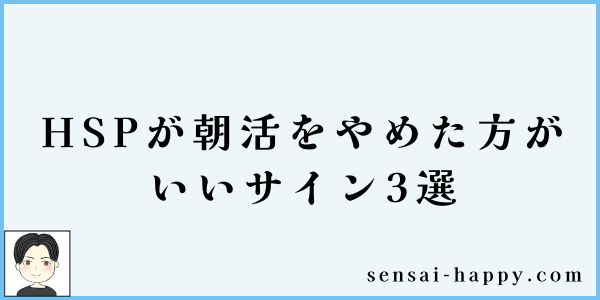
HSPが朝活をやめた方がいいサイン3選を紹介します。
- 起きることが毎日プレッシャー
- 一日中ぐったりしているなら休息を優先
- やらなきゃいけないことになっている
ゆっくり見ていきましょう。
1.起きることが毎日プレッシャー
HSPさんはまじめで責任感が強く、「朝活を続けなきゃ」と義務感にとらわれやすい傾向があります。
もし「また早起きできなかった…」と、毎朝自己嫌悪になってしまう場合は、心が疲れているサインなんです。
朝活は「やりたいからやる」ものであって、「やらなきゃいけない」になってしまうと、HSPさんの繊細な心をすり減らす原因になってしまいます。
Grevenら(2019)の研究では、HSPさんは“失敗への過敏な反応”をしやすいとされており、習慣がプレッシャーになることが疲労や不調を引き起こすと示唆されています。

あなたが朝の時間に心地よさよりストレスを感じているなら、無理に続けなくていいんです。

「やらない選択」も、あなたを守る立派なセルフケアなんだよ!
2.一日中ぐったりしているなら休息を優先
朝活をしているのに日中ずっとだるく、集中力が続かない…ということはありませんか?
それは、あなたの身体が“もっと休んでほしい”と訴えているサインかもしれません。
特にHSPさんは、刺激による疲労の回復に人一倍時間がかかると言われており(Aron & Aron, 1997)、しっかり眠らないとパフォーマンスが著しく落ちることもあります。

朝活は元気を引き出す手段であるはずなのに、疲労感が強まっているなら本末転倒なんです。
その場合は、朝活よりもまず「睡眠の質と量をしっかり確保すること」が先決です。

あなたが元気に過ごせることが一番の優先事項なんだよ!
3.やらなきゃいけないことになっている
HSPさんは周囲に合わせる傾向が強く、「〇〇さんがやってるから私もやらないと」と思ってしまいやすいんです。
朝活が“やりたくてワクワクする時間”から、“やらないといけない義務”になっているとき、心のモチベーションはすでに下がっている可能性が高いんですよね。
本来、朝活はあなたの一日を心地よくスタートするための“ごほうび時間”のはずです。
それが“消耗の時間”になっているのなら、いったん立ち止まって見直すことが必要ですよね。

Aron博士の研究でも、HSPさんの幸福感は「外的な成果」より「内面の充実感」によって高まるとされています。

朝活があなたの心を豊かにしていないなら、それは“やめる”サインだよ!
HSPのよくある質問

HSPのよくある質問をまとめました。
- 1人になりたい
- 人に頼れない
- スピリチュアル
- 苦手なこと
- 自己肯定感
1つずつ見ていきましょう。
1人になりたい
「1人になりたいと思うことがよくあります」という相談。

自己成長できるチャンスだよね!

1人時間を上手に使って目標達成していきましょう◎
人に頼れない
「人に頼れないことが悩みです」という相談。

頼れない原因を知っている?

いっしょに解決方法を見ていきましょう◎
スピリチュアル
「スピリチュアルをしたら何か変わりますか?」という相談。

行動が鍵だよ!

相性に関しては下記記事で解決しています。
苦手なこと
「HSPが苦手なことを教えてください」という相談。

苦手なことは15こあるよ!

苦手から距離を取る対策を10こ紐解いています◎
自己肯定感
「自己肯定感を高めるにはどうしたらいいか知りたいです」という相談。

テクニック11こを解説しているよ!

自己肯定感を高めて、維持するテクニックが学べます◎
HSPの私・体験談

HSPの私・体験談を紹介します。
- 睡眠時間は8時間(多くて9時間)
- 寝すぎるとよくない
- 睡眠を削ってよかったことはない
1つずつ解説します。
睡眠時間は8時間(多くて9時間)
睡眠時間は結局、質です。
長ければいいというわけではありません。
自分の体で実験しましたが、8時間睡眠が体の疲れをしっかりとってくれました。
7〜9時間の睡眠で、脳は日中の情報を整理し、記憶を定着させ、感情のバランスを整えることができます。
特にレム睡眠とノンレム睡眠のサイクルを複数回確保するには約8時間が理想とされているんです。引用:Walker, M. (2017). Why We Sleep./Hirshkowitz et al., 2015, National Sleep Foundation
科学的にみても、8時間睡眠を推奨しています。
寝すぎるとよくない
9時間以上の睡眠は、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、だるさや集中力の低下につながりやすいんです。
過眠はうつ症状や代謝異常とも関係があるとされており、適度な睡眠が心身の健康維持に必要なんです。引用:Cappuccio et al., 2010, Sleep/National Sleep Foundation
よっぽど何かの病気にかかっているわけでないのなら、寝過ぎてもいいことはありません。
しかし、働きすぎたり、気を使いすぎる日が連続するとHSPさんの睡眠時間は長くなります。
私も行事ごとや、いつも以上に緊張するような仕事の日は、疲れが夕方から出ていたので日によっては9時間睡眠の時もありました。

いきすぎた睡眠時間は体によくないのは事実なので、いつも通りに起きて昼寝をする方が◎
睡眠を削ってよかったことはない
睡眠時間を削っていいことはありませんでした。
6時間睡眠を2週間続けた被験者の注意力・反応速度・論理的思考力は、一晩徹夜した人や、血中アルコール濃度が0.1%の酩酊状態と同等のレベルまで低下していた。
引用:アメリカのペンシルベニア大学とワシントン州立大学の共同研究(Van Dongen et al., 2003)
6時間睡眠だと脳が酔っ払った人と同じくらい認知度が下がるといわれています。
なので、現在は8時間睡眠をキープしていて、昼寝を30分くらいすることを継続しています。

自分の調子に合わせてみてくださいね!

早めに体を休めると疲れも早く取れるよ◎







