
HSPとエンパスのちがいを教えて!

いいよ!詳しく解説するね!
前半では、HSPとエンパスのちがいについて解説します。
後半では、エンパス体質と上手に付き合う3つのヒントを紹介しますよ!
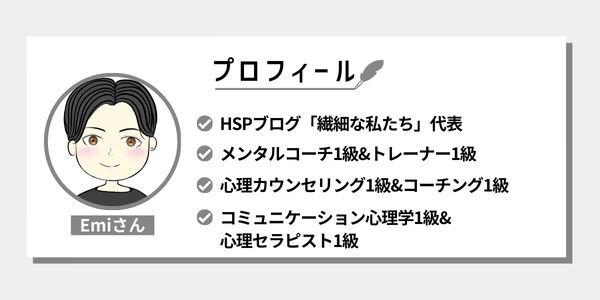

HSPとエンパスの違いとは?
HSPさんとエンパスは、どちらも「共感力が高い」特徴を持っています。
ただし、細かく見るとその敏感さの“種類”に違いがあるんです。
HSPさんは五感や内面の刺激に反応しやすく、環境や人の感情の変化に敏感に気づいてしまいます。

一方、エンパスは相手の感情やエネルギーを自分のことのように感じ取ってしまう特性を持っています。
例えば、隣の人が落ち込んでいると、まるであなた自身の感情のように心が重くなることがあります。
このような「感情の吸収力」が強いのがエンパスなんです。
HSPさんが感受性が高い観察者であるのに対し、エンパスは感情を取り込む共感者と言えるかもしれません。

心理学的には、HSPさんはエレイン・アーロン博士が提唱した神経的敏感性に基づく概念として、脳の扁桃体の反応の強さが指摘されているね!
一方、エンパスは科学的な定義が曖昧で、スピリチュアルな領域でも扱われるため、個人の体験ベースで理解されることが多いんです。
HSPとエンパスは重なることもある
HSPさんとエンパスは、まったく別物ではなく、重なる人もいるんです。
つまり、音や匂い、光に敏感なHSPさんでありながら、人の感情や場の空気を強く「吸収」してしまうエンパスの特徴も持っている場合があります。
このような人は、日常生活での疲れやすさが特に強く出やすい傾向があります。

例えば、人混みや会議の場などでは、周囲の感情が一気に押し寄せてしまい、ぐったりしてしまうことがあるんです。
実際、2020年の米国の心理学ジャーナルでは、「共感性が高い人は自己境界の脆弱性により、情緒的バーンアウトを起こしやすい」と指摘されています。
HSPさん×エンパスの組み合わせは繊細であると同時に、とても深い理解力と優しさを持っているという強みもあるんです。
だからこそ、自分の感覚を正しく知っておくことが、安心して過ごす第一歩になります。
あなたの“共感疲れ”、実はエンパスの影響かも?
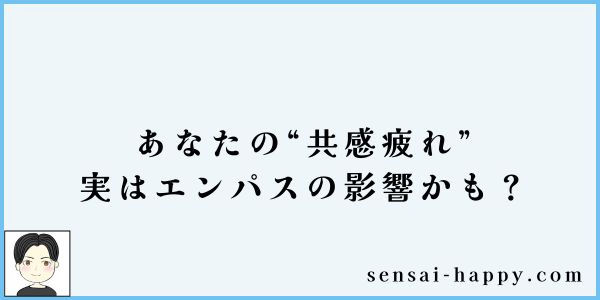
あなたの“共感疲れ”、実はエンパスの影響かも?について解説します。
- 共感疲れとはどんな状態?
- エンパスの特徴が「共感疲れ」に関係する理由
- 「共感疲れ」が続くとどうなる?
- 自分を守るために、共感を「切る」意識も必要
1つずつ見ていきましょう。
1.共感疲れとはどんな状態?
共感疲れとは、他人の気持ちに強く反応しすぎてしまい、自分のエネルギーが消耗してしまう状態のことを指します。
特にHSPさんやエンパス体質の人は、人の悲しみや怒りを自分のことのように感じてしまいやすく、知らないうちに心がぐったりしてしまうんです。
例えば、友人の愚痴を聞いているだけで、あなたまでどっと疲れてしまうような場面がそうです。

これは「共感性疲労(empathic distress)」という心理現象として知られています。
心理学者バビエリの研究でも、共感性が高い人は感情移入しやすく、ストレスホルモンの分泌が増加しやすいことが示されています。
つまり、あなたの優しさが“心の体力”を削ってしまうことがあるんです。
2.エンパスの特徴が「共感疲れ」に関係する
エンパスの人は、相手の感情や雰囲気を“受け取ってしまう”ような感覚を持っています。
HSPさんが「感じやすい」なら、エンパスは「吸い込みやすい」という表現が近いかもしれません。
例えば、明るくふるまっている相手の“隠れた悲しみ”まで、なぜか感じ取ってしまうことがあるんです。

そのため、会話のあとに疲れたり、理由もなく心が沈んだりすることが起きやすくなります。
これは、「ミラーニューロン」の過活動とも関係しているとされています。
ミラーニューロンとは、相手の表情や感情を脳内で“模倣”する神経のことで、共感性の根本にある仕組みです。
この神経が活発なエンパスは、人の感情をリアルに“体感”してしまうため、心が消耗しやすくなるんです。
3.「共感疲れ」が続くとどうなる?
共感疲れが慢性化すると、
- 気力が出ない
- 人と会いたくない
- 眠れない
といった状態に陥ることがあります。
人との関わりが本来は好きなのに、「関わると疲れるから避けたい」と感じてしまうようになるんです。
これは、心理学でいう情緒的バーンアウト(emotional burnout)の一種です。
研究によると、共感性が高い人ほどバーンアウトのリスクが高まる傾向があります(Figley, 1995)。

エンパス体質のHSPさんは、人の気持ちに寄り添う力があるぶん、自分の感情と他人の感情の区別がつきにくくなることもあるんです。

その結果、知らないうちに心がいっぱいになってしまい、疲れやすさにつながってしまうんだ
4.共感を「切る」意識も必要
共感疲れを防ぐには、共感しすぎない練習も大切なんです。
「共感=いいこと」ではなく、「共感しすぎは危険」と捉えることも必要です。
例えば、友達の悩みを聞くときに「それは大変だったね」と受け止めるだけにとどめて、「なんとかしてあげたい」とまでは背負わない意識を持つようにしてみてください。

これは「共感的境界線」という考え方で、自分と他人の感情の間に“心のバリア”をつくるイメージです。

カナダの心理学者キンデルによれば、こうした境界線があることで、共感を保ちつつ疲労を防げることが明らかになっているよ!
HSPエンパスが疲れやすい5つのシーン
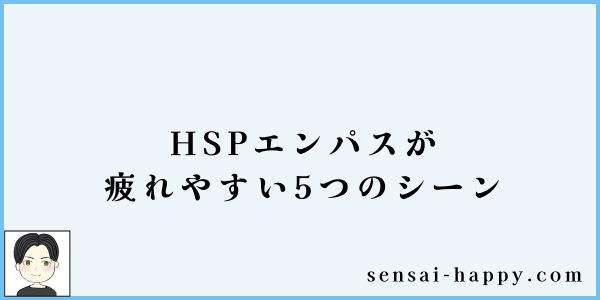
HSPエンパスが疲れやすい5つのシーンを解説します。
- 人混みにいるとき
- 感情的な話を聞いたあと
- ネガティブな空気の職場や家庭
- 長時間の対人コミュニケーション
- 頑張りすぎたあとにひとりになるとき
ゆっくり見ていきましょう。
1.人混みにいるとき
HSPエンパスさんは、周囲の雰囲気や感情を無意識にキャッチする力があるため、人混みでは多くの情報を一気に受け取ってしまうんです。
例えば、
- 駅
- ショッピングモール
などでは、他人のイライラや疲れを感じ取ってしまうこともあります。
これは「感覚過敏」と「感情共感」が重なることで、脳がオーバーヒートしてしまうからなんです。
実際、Aron博士の研究でも、HSPさんは視覚・聴覚などの刺激に対して脳が強く反応しやすいとされています。

エンパス体質の人は、他人の感情エネルギーを吸収しやすいとも言われています。

そのため、短時間の外出でもドッと疲れることがあるんだ
2.感情的な話を聞いたあと
悩み相談やネガティブな話を聞いたあとに、なぜか自分の方がぐったりしてしまうという経験はありませんか?
HSPエンパスさんは、相手の気持ちに深く共感する力があるため、感情を“もらいやすい”傾向があります。
例えば、友達の怒りや悲しみを聞いているうちに、自分も怒りや悲しみを抱えたように感じてしまうことがあるんです。
これは「ミラーニューロン」と呼ばれる神経回路が関係しています。

心理学の研究によると、共感性が高い人は他人の情動に同調しやすく、脳内で実際に体験しているかのような反応が起こると言われています。

そのため、話を聞いただけでも深く疲れてしまうんだ
3.ネガティブな空気の職場や家庭
HSPエンパスさんは、場の空気にとても敏感なため、ピリピリした雰囲気に長時間いると心がすり減ってしまうんです。
例えば、職場で誰かが怒られている場面や、家族同士の不機嫌な会話など、直接関係ないはずの出来事にも強く反応してしまうことがあります。
これは「雰囲気共感」とも言える反応で、心理学的には“情動感染”と呼ばれる現象に近いです。

周囲のストレスが自分のもののように感じられてしまい、結果としてその場にいるだけで疲れやすくなるんです。
4.長時間の対人コミュニケーション
会話が続く場面では、HSPエンパスさんは
- 相手の表情
- 言葉
- トーン
など、あらゆる情報を読み取りながら対応しようとする傾向があります。
そのため、人と話しているだけで神経をすり減らしやすいんです。
例えば、会議や長時間のZoom会議などでは、相手の反応を逐一気にしてしまい、会話後にぐったりすることもあります。

共感力が高いというのは素晴らしいことですが、それが「疲れ」の原因にもなってしまうんです。
研究によれば、共感性の高い人ほど“社会的神経疲労”を感じやすいとされており、自分の感情と他人の感情の境界があいまいになることで消耗しやすくなります。
5.頑張りすぎたあとに1人になるとき
HSPエンパスさんは、人前で無理に元気にふるまってしまうことが多いため、あとで反動のような疲れがやってくることがよくあります。
例えば、友達との集まりで気を使いすぎたり、仕事でテンションを上げ続けた日の夜など、「やっと1人になれた」と思った瞬間に心がどっと疲れを感じることがあるんです。
これは「社会的仮面(social mask)」をかぶり続けたことによる疲労反応で、特に繊細な神経を持つHSPさんには起こりやすい傾向があります。
神経科学でも、過剰な自己抑制はストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を高めるとされていて、長期的に心身に影響が出る可能性があるんです。
HSPエンパスの気質は才能
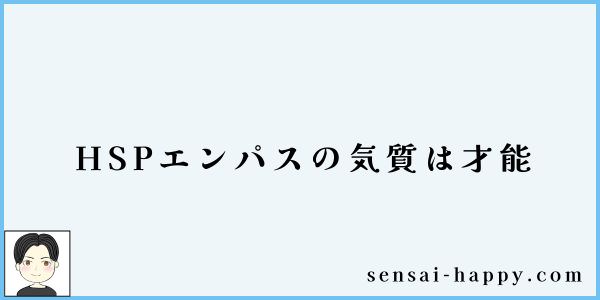
HSPエンパスの気質は才能5点について解説します。
- 繊細さは「気づける力」
- 他人を癒す力に変えられる
- 物事の本質を見抜く力
- 集団の潤滑油になる
- 自分を大切にする
1つずつ見ていきましょう。
1.繊細さは「気づける力」
HSPエンパスさんは、他の人が気づかないような微細な変化を察知する力を持っています。
例えば、相手の声のトーンや表情の変化、小さな場の違和感にすぐに気づくんです。
この「気づける力」は、仕事でも人間関係でも重要なスキルになります。
特に
- 医療
- 教育
- カウンセリング
などの場面では、繊細な観察力が大きな役割を果たします。
アーロン博士の研究によれば、HSPさんの脳は五感からの情報を深く処理する特徴があることが明らかにされています。

つまり、あなたの「感じすぎる」は、見えないものに気づける才能でもあるんです。
2.他人を癒す力に変えられる
HSPエンパスさんは、他人の感情をまるで自分のことのように感じられる共感力を持っています。
これは「過敏だから」ではなく、「人の気持ちを理解できる能力」なんです。
例えば、友達が落ち込んでいるとき、何も言われなくてもその変化に気づけるあなたは、そっと寄り添うことができる存在です。
心理学の研究でも、共感力の高い人ほど相手のストレスを軽減する力があると報告されています。

つまり、あなたのその優しさは、ただの性格ではなく、人を救う力に変わる“資質”なんです。
3.物事の本質を見抜く力
HSPエンパスさんは、ひとつの出来事を何度も深く考えたり、物事の裏側まで読み取ろうとする傾向があります。
「考えすぎ」と言われてしまうこともありますが、それは“鋭い洞察力”の裏返しなんです。
例えば、他の人がスルーするような些細な違和感をあなたが見抜けることがあるはず。
実際、米国心理学会によれば、高い自己内省性(self-reflection)は創造性や問題解決能力と関連があると報告されています。

つまり、あなたの思慮深さは、クリエイティブな才能の一部なんです。
4.集団の潤滑油になる
HSPエンパスさんは、誰かの緊張や怒り、悲しみといった空気の変化をすぐに感じ取ります。
これは、他の人が言葉にしない“感情の温度”を読む才能なんです。
例えば、誰かの小さな違和感に気づいて、トラブルを未然に防ぐことができたりします。
この能力は、チームや家族などの集団の中で、場を和ませたり、円滑なコミュニケーションを生むための重要な役割を果たします

これは「疲れやすい」ではなく、「空気を整える力を持っている」ということなんです。
5.自分を大切にする
HSPエンパスさんの気質は、とても繊細でパワフルです。
でもその分、外部からの刺激に疲れやすく、無理をしすぎるとバランスを崩してしまうこともあります。
だからこそ、「休むこと」や「距離を取ること」は、あなたの才能を守るための大切な行動なんです。
心理学者カール・ロジャーズは、「まず自分が満たされることで他者にも与えられる」と述べています。

つまり、自分を大切にすることが、あなたのやさしさや感受性を本当の意味で活かす力になるんです。
エンパス体質と上手に付き合う3つのヒント
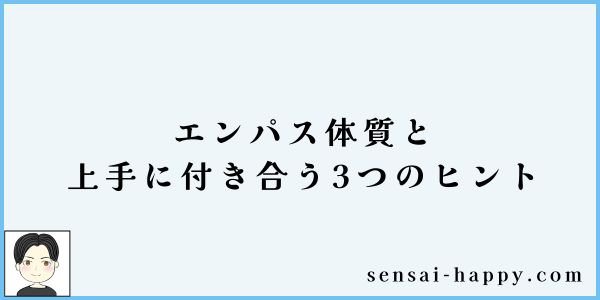
エンパス体質と上手に付き合う3つのヒントを解説します。
- 感情の“境界線”を意識する
- 一人の時間でエネルギーをリセット
- 自分の感情を言葉にして整える
1つずつ見ていきましょう。
1.感情の“境界線”を意識する
エンパス体質のHSPさんは、相手の気持ちを深く感じ取りすぎて「まるで自分の感情みたい」と混乱することがあるんです。
だからこそ、
- 「これはあなたの感情」
- 「これは他人の感情」
と心の中で線引きすることが大切。
例えば、ネガティブな話を聞いたあとに気分が落ちたとき、「これはあの人の不安を受け取ったんだ」と自覚することで、気持ちが整理しやすくなります。
心理学では「感情的同一化(emotional identification)」を手放すことでストレスが軽減されると言われています。

つまり、共感しすぎるあなたこそ、意識的に“分ける力”を持つことが心を守るカギなんです。
2.一人の時間でエネルギーをリセット
エンパス体質のHSPさんは、人と関わるだけで情報や感情を大量に受け取ってしまうため、脳が常にフル稼働している状態になりやすいんです。
だからこそ、「何もしない静かな時間」がとても重要なんです。
例えば、
- 1日15分でもスマホを置く
- 音のない空間で深呼吸する
だけで、感覚が整いやすくなります。
研究によると、過敏な神経系は外部刺激からの回復に時間を必要とする(Aron, 2010)と報告されています。

つまり、あなたが「一人になりたい」と思うのは甘えではなく、脳の自然な回復反応なんだ
3.自分の感情を言葉にして整える
エンパス体質のHSPさんは、相手の気持ちを察するのは得意でも、自分の感情を言葉にするのが苦手な傾向があります。
でも、感じたことを言葉にすることで、頭の中が整理されて心が軽くなるんです。
例えば、「今日はなんだか疲れた。あの人の焦りを感じすぎたのかも」と紙に書くだけでも効果があります。
心理学ではこれを「ラベリング」と呼び、感情を名前で呼ぶことでストレスを軽減する効果がある(Lieberman et al., 2007)とされています。

あなたの繊細さを守るために、感情を“言葉にする力”を育てていくことがとても役に立つんです。
HSPのよくある質問

HSPのよくある質問をまとめました。
- HSPとの向き合い方
- 苦しさを感じる
- 人嫌いになれない
- HSPが持つ静かな魅力
- HSP気質はデメリット
1つずつ見ていきましょう。
HSPとの向き合い方
「HSPとの向き合い方を教えてください」という相談。

向き合うときに悩みやすい壁を解説しているよ!

得られる変化を学ぶことができます。
苦しさを感じる
「HSPでいることが苦しく思えるときがあります」という相談。

そうだったんだね

繊細を強みに変えるヒントを見てみませんか?
人嫌いになれない
「嫌った方がいい人がいても、なかなか嫌えなくて」という相談。

それはきついね

罪悪感との向き合い方までを解説しています。
HSPが持つ静かな魅力
「HSPが持つ静かな魅力について教えてください」という相談。

4つの魅力を解説しているよ!

活躍している実例を見てみましょう!
HSP気質はデメリット
「HSP気質はデメリットですか?」という相談。

そんなことはないよ!

疲れを和らげるためにできることを7つ紹介しています!
HSPの私・体験談

HSPの私・体験談を紹介します。
- エンパスある
- HSPもある
- コーチングで活かす
あなたの励みになったら嬉しいです。
エンパスある
人の感情を人以上に取り込んでしまうこの感覚は、エンパスだということを最近知りました。
なんというか、HSPだけではない何かも持っているんだろうなと薄々思っていたんですけど、やはり。
人の感情に影響される力が大きいので関わる人は選ぶようにしています。
HSPもある
外の影響も受けるので、ほんとに気疲れが半端ないんですよね。
たくさんの人と関わった日なんてぐったりです。
今の働き方では、個人で仕事をすることで疲れやすさから解放されました◎
コーチングで活かす
適応障害になったりと、いろんな嵐が次々にきましたが、乗り越えることでたくさんの虹を見ることができました。
この特性をコーチングで活かすことができるのでとってもうれしいです◎

いっしょにたくさんチャレンジできたらしあわせです!

たくさん挑戦していこうね!

















