
HSPさんは、人を嫌いになれないの?

嫌いになることに、罪悪感を持つ人はいるかな!
前半では、HSPさんが人を嫌いになれない3つの理由を解説します。
後半では、あなたが疲れないための工夫を5つ紹介していきますよ!
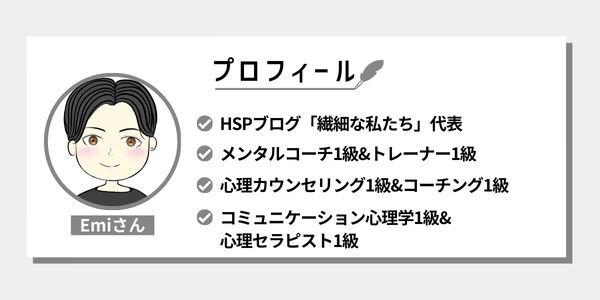

HSPが人を嫌いになれない3つの理由

HSPが人を嫌いになれない3つの理由を解説します。
- 相手の気持ちを深く想像する
- 嫌うこと=悪いことだと感じてしまう
- 相手の“いい面”も同時に見えてしまう
1つずつ見ていきましょう。
1.相手の気持ちを深く想像する
HSPさんは、共感力が非常に高いため、相手の感情や背景を自然と想像してしまいます。
例えば、誰かに嫌なことをされたとしても、
- 「この人もつらいのかも」
- 「何か事情があるのかもしれない」
と考えてしまうんです。
その結果、相手を嫌うことに強い抵抗を感じてしまいやすいんですね。
心理学では、HSPさんのように感受性が高い人は「感情の共鳴性」が強く、他者の苦しみに心が引っ張られやすいと報告されています(Acevedo et al., 2014)。

つまり、「嫌う」よりも「理解しよう」とする気持ちが自然に出てくるんです。
あなたが人を嫌いになれないのは、やさしさでもあり、感受性の高さからくる反応なんですよ。
そのままのあなたを責める必要はまったくないんです。
感じすぎる心を、どう守るかが大切なんですよ。

まずは「嫌えない自分」を認めてあげてね!
2.嫌うこと=悪いこと
HSPさんは、道徳心や良心が強く、「人に対して嫌な感情を持ってはいけない」と無意識に思ってしまうことがあります。
例えば、誰かを「苦手だな」と思っても、「そんなことを思う私は冷たいのでは」と自分を責めてしまうことがあるんです。
これは、
- 「優しくあるべき」
- 「みんなと仲良くすべき」
といった価値観に敏感なHSPさんだからこその感覚なんです。
心理学の研究でも、HSPさんは「道徳的感受性(moral sensitivity)」が高く、罪悪感や自己否定を感じやすい傾向があるとされています(Liss et al., 2008)。

つまり、「嫌ってはいけない」と思い込んでしまいやすい傾向があるんですね。
でも、誰かを嫌う気持ちそのものは、人として自然な感情なんですよ。
嫌ってしまう自分を受け入れることも、自己理解にはとても大切なんです。
あなたが「嫌えない」ことに疲れを感じるなら、それは無理をしているサインかもしれません。

やさしさと境界線は、ちゃんと両立できるんだ
3.相手の“いい面”も同時に見えてしまう
HSPさんは、人の内面を深く見つめる力があり、どんな相手にも「いいところ」を見つけてしまう傾向があります。
例えば、嫌なことをされたとしても、「でもあの人にも優しい一面があったし…」と、すぐにプラスの面に意識が向いてしまうんです。
このように、相手を一面的に見ず、全体像を見ようとすることはHSPさんの強みですよね。

ただし、そのバランス感覚ゆえに、「完全に嫌う」ことができず、心の中に葛藤を抱えてしまうこともあります。
認知心理学でも、HSPさんは「全体処理傾向(global processing)」が強く、情報を複数の視点からとらえやすいことが知られています(Aron & Aron, 1997)。
つまり、悪いところだけを見て判断することが難しいんですね。
あなたが人を嫌えないのは、「その人の全体」を見てしまうからなんです。

それはとても豊かな感性であり、あなたの魅力でもあるんですよ。
ただし、自分を守る視点も忘れずに持っていてくださいね。
“やさしい目”と“境界線”は、どちらもあなたを助けてくれるんです。
抱える“罪悪感”との向き合い方5つ
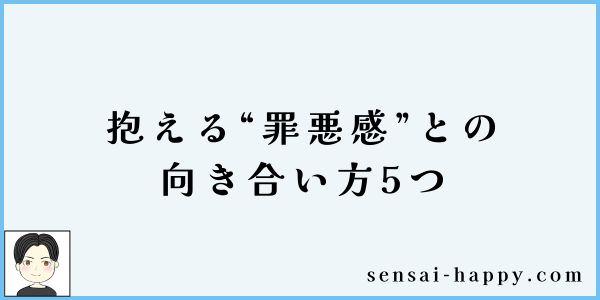
嫌いになれないHSPさんが抱える“罪悪感”との向き合い方5つを解説します。
- 「嫌う=悪いこと」と思い込んでいる思考に気づく
- “いい人でいなきゃ”という思い込みを手放す
- 「感情」と「行動」は別もの
- 「嫌いになれない=優しさ」ではなく「境界線の弱さ」
- 自分を守ることは“相手のため”にもなる
1つずつ見ていきます。
1.「嫌う=悪いこと」と思い込んでいる
HSPさんは、思いやりが強いぶん、「誰かを嫌うこと=悪」と感じてしまいやすいんです。
例えば、嫌な人がいても「私が悪いのかも」と自分を責めてしまうことがありますよね。
でも、その思考は、子どものころから植えつけられた“優等生思考”のクセかもしれません。
心理学ではこれを「認知の歪み」と呼び、HSPさんは特に「過度な責任感」による自己批判傾向が強いとされています(Liss et al., 2008)。

まずは、「誰かを嫌うこと自体は、人として自然な感情なんだ」と、自分にやさしく声をかけてみてください。
感情を持つことと、それをどう行動に移すかはまったく別なんです。
あなたが誰かを嫌だと感じても、それだけで“悪い人”にはなりません。
まずは、湧いてきた感情を否定しないところから始めてみましょう。

感情を認めることが、罪悪感を和らげる第一歩なんだよ
2.“いい人でいなきゃ”という思い込み
HSPさんは、まわりから
- 「やさしい人」
- 「気が利く人」
と見られることが多いため、その期待に応えようと頑張りすぎてしまうことがあります。
例えば、嫌なことを言われても「ニコニコしていなきゃ」「傷ついたなんて思われたくない」と振る舞ってしまいがち。
でも、それは「自分を犠牲にしてでも、いい人でいたい」という思考のパターンなんですよね。
認知行動療法でも、「役割期待にこたえすぎる人ほど、罪悪感を抱えやすい」という研究があります(Beck, 1979)。

「いい人でいなきゃ」を手放すことで、あなたの心に余白が生まれてくるんです。
やさしさは、相手に合わせることだけではなく、自分を大切にする行動にも表れるんですよ。
誰にでもいい顔をする必要はありません。
あなたの心が苦しくならない範囲で関わっていいんです。

“やさしくて苦しい”を、“やさしくて心地いい”に変えていこうね!
3.「感情」と「行動」は別もの
HSPさんは、人にネガティブな感情を持つと、それだけで「ひどいことをしている」と感じてしまうことがあります。
でも、感情を抱くことと、それを実際に誰かにぶつけることは別のことなんですよ。
例えば、「あの人、ちょっと苦手」と思っても、態度に出さず距離を取っているだけなら、誰も傷ついていません。
心理学では、感情と行動を切り分けることを「感情の脱同一化(Emotional Diffusion)」と呼び、ストレス低減に有効とされています(Hayes et al., 1999)。

あなたが人を嫌いになることを恐れる必要はないんです。
大事なのは、その気持ちとどう向き合い、どんな行動をとるかなんです。
感情は「一時的な波」のようなもの。
悪者にするより、「あ、今こんな気持ちがあるな」と認めてあげましょう。

その認識があるだけで、ずいぶん気持ちは軽くなるんだ
4.「嫌いになれない=優しさ」ではない
HSPさんは、人との距離感に敏感で、「相手を嫌うくらいなら、自分が我慢した方がいい」と考えがち。
でも、その感覚は“やさしさ”というより、“心の境界線が曖昧”な状態かもしれません。
例えば、
- 「本当は距離を取りたいのに断れない」
- 「会うと疲れるのに連絡してしまう」
といった行動をしてしまうことってありますよね。
心理学では「境界線(バウンダリー)」という概念があり、これが適切に引けないと、自分の感情がまわりに振り回されてしまうといわれています(Cloud & Townsend, 1992)。
“嫌わない努力”ではなく、“健やかな線引き”が必要なんです。

あなたの心を守ることは、わがままではなく、誠実な自己配慮なんですよ。
「嫌っていないけど、少し距離を置こう」という考え方でOK◎
近づきすぎないことで、優しさを保てる関係もあるんです。

あなたが心地よくいられる距離感を、大切にしてみてね!
5.自分を守ることは“相手のため”に
HSPさんは、「自分さえ我慢すれば、相手が傷つかずにすむ」と思ってしまいがちです。
でも、本当にそうでしょうか?
あなたが無理して関わっているとき、相手もその“ぎこちなさ”を感じ取っている可能性があるんです。
心理学では「情動伝染(emotional contagion)」という概念があり、感情は無意識に周囲に伝わることがわかっています(Hatfield et al., 1994)。

つまり、あなたが我慢していればいるほど、関係は自然さを失っていくということなんです。
あなたが自分を大切にすることで、相手との関係もより誠実になっていくんですよ。
罪悪感ではなく、“誠実さ”をもって距離を選ぶことが、相手にも優しい選択なんです。
自分を守ることは、まわりにとってもプラスになります。

だからどうか、「離れることは、優しさの一つ」と思ってみてね!
あなたが疲れないための工夫5
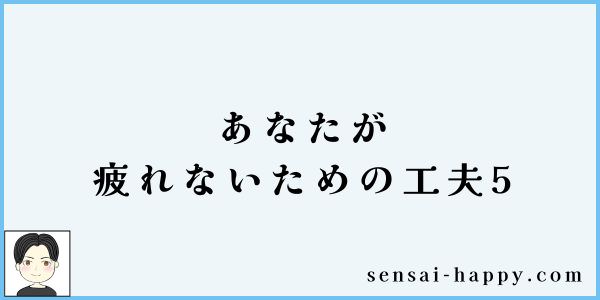
あなたが疲れないための工夫5つを解説します。
- 「やりすぎたかな?」と感じたら、少し立ち止まってみる
- 「頼まれても即答しない習慣」を持つと疲れにくくなる
- 「自分の予定・体調・気分を優先してもいい」と許可する
- 「優しさの使いどころ」を選べるようになる
- 「ひとり時間」で心を回復させる習慣を持つ
1つずつ見ていきます。
1.少し立ち止まってみる
HSPさんは、相手の気持ちを細かく察知できるぶん、「もっと優しくしなきゃ」と思って無理をしてしまいやすいんです。
例えば、断れないお願いを引き受けたり、自分の予定より相手を優先してしまったりすることがありますよね。
でも、“やさしさ”がオーバーワークになると、心のエネルギーは消耗してしまうんです。
心理学でも「過剰適応(over-adaptation)」という概念があり、自分のニーズを抑えすぎることは慢性的なストレスにつながるとされています(Liss et al., 2008)。
そんなときは、
- 「ちょっと疲れてない?」
- 「本当はどうしたい?」
と、自分に問いかける時間をつくってみてください。

優しさを相手に向ける前に、まずは自分にやさしくすることが何より大切なんですよ!
無理をする優しさは、長く続かないんです。
だからこそ、“がんばりすぎサイン”に早めに気づいてあげましょう。

あなたの心は、あなたが守ってあげる必要があるんだよ!
2.頼まれても即答しない習慣を持つ
HSPさんは、頼られると断れなかったり、「すぐ返事しなきゃ」と焦ってしまう傾向があります。
でも、その場で返事をすると、つい相手の気持ちを優先してしまい、自分の意志が後回しになりがちなんです。
例えば、頼まれごとをされてすぐ「うん、いいよ」と答えたあとに、あとから「やっぱりしんどい…」と後悔することはありませんか?

こうした“自動的な即答”は、HSPさんにとってエネルギーの浪費につながります。
心理学でも「選択の一時停止(choice deferral)」は、ストレスを軽減する行動として有効とされているんです。(Baumeister et al., 1998)。
- 「確認してから返事しますね」
- 「一度考えてもいいですか?」
というワンクッションを入れるだけで、あなたの心はぐっと守られるんですよ。
即答しないことで、冷静に「今、本当にやれるかどうか」を判断できます。
やさしさの前に、判断の余白を持つことが、疲れにくさにつながるんです。

一度立ち止まることで、やさしさを“無理なく続けられる形”に変えていけるんだ!
3.自分の予定・体調を優先してもいい
HSPさんは、相手に嫌われたくない気持ちや、相手の気持ちを傷つけたくない思いが強くなりすぎることがあります。
その結果、「ちょっと無理だけど…まあいいか」と、自分を押し殺してしまうことがあるんですよね。
でも、“断ること”や“休むこと”は、わがままではなく正当な自己配慮なんです。
心理学では「自己受容(self-acceptance)」がストレス耐性を高める要因として働くことがわかっています(Neff, 2003)。

あなたがあなたらしくいるためには、自分の気持ちや体の声に正直になることが必要なんです。
- 「今日は疲れてるからやめておこう」
- 「これは私のキャパを超えてる」
と気づいたら、無理せず手を引いていいんですよ。
あなたの優しさを“持続可能なもの”にするためには、自分を後回しにしないことが大切なんです。
まずは「私を大切にしていい」と、心の中で許可を出してあげてくださいね。

あなたが満たされてこそ、やさしさはあたたかく届いていくんだよ
4.優しさの使いどころを選ぶ
HSPさんは、どんな相手にも平等にやさしくしようとする傾向があります。
でも、本当にあなたの優しさを大切にしてくれる人と、そうでない人がいるのも現実なんです。
例えば、
- 何度も同じように甘えてくる相手
- 都合のいいときだけ頼ってくる人
に対しても、断れずに対応してしまうことってありますよね。

そういった関係性が続くと、「私はどうしてこんなに疲れるんだろう」と感じるようになります。
心理学では「対人境界線(boundaries)」の設定が健康な人間関係に必要とされており、HSPさんはその線引きが苦手な傾向にあるといわれています(Cloud & Townsend, 1992)。
やさしさを“無差別に”使うのではなく、“必要なところに届ける”意識があると心がラクになるんです。
誰かに断ることは、冷たさではなく、信頼を守るための行動でもあるんですよ。

あなたのやさしさは、ちゃんと選んで使っていいんだ
選べることで、あなたの心はもっと元気でいられるようになるんですよ。
5.「ひとり時間」で心を回復させる
HSPさんは、やさしくしようとすると、それだけでエネルギーを多く消費してしまいます。
だからこそ、“与えるだけ”ではなく“回復させる時間”を意識的に取ることがとても大切なんです。
例えば、誰かと話した後に疲れを感じたら、静かな部屋でお茶を飲んだり、好きな本を読んだりする時間をつくってみてください。
脳科学の研究でも、HSPさんは刺激処理が深いため、休息によるリカバリーが非常に重要であると示されています(Acevedo et al., 2014)。

あなたが誰かに優しくするほど、自分の心にもやさしさを返してあげてください。
与えるだけのやさしさでは、いずれ疲れきってしまうんです。
ひとりの時間を通して、心のエネルギーを“再充電”していきましょう。
その積み重ねが、あなたらしいやさしさをずっと保ち続ける秘訣なんですよ。

「やさしくすること」と「自分を守ること」、どちらも両立していいんだよ!
嫌えないことが悪いわけではない理由5
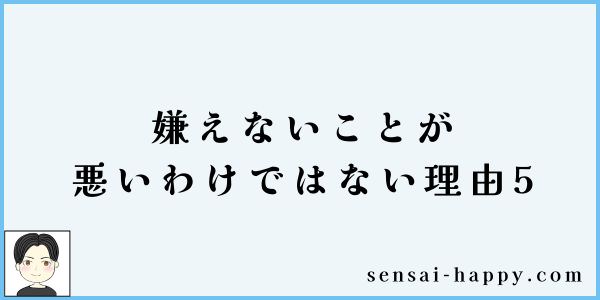
嫌えないことが悪いわけではない理由5つについて解説します。
- 感じやすいあなたの「共感力」は強み
- 人間関係をやわらかくしてくれる
- 人間関係を育てる力になる
- 優しさを守る方法をまだ学んでいないだけ
- 人は安心していられる
1つずつ解説します。
1.あなたの「共感力」は強み
HSPさんは、相手の表情や声のトーン、小さな変化にも敏感に気づくことができます。
その結果、誰かを嫌おうとしても「この人にもつらい背景があるのかも」と、相手の気持ちに共感してしまうんです。
例えば、きついことを言われたとしても、「本当は疲れてるのかもしれない」と想像してしまうことはありませんか?
心理学では、HSPさんのような高い感受性を「感情共鳴性(emotional resonance)」と呼び、他者への共感力が高いことがわかっています(Liss et al., 2008)。

つまり、あなたが嫌えないのは“やさしすぎるから”ではなく、“人の心を感じる力が強いから”なんです。
共感力は、人と深くつながるためにとても大切な力なんですよ。
その力があるからこそ、誰かにとって「安心できる存在」になれているんです。
あなたの感じやすさは、けっして悪いものではありません!

それは、あなたの大切な資質なんだよ!
2.人間関係をやわらかくしてくれる
HSPさんは、人の“良いところ”と“苦手なところ”を同時に見ることができます。
例えば、嫌なことをされた人に対しても、「でもあの人にもこういう面があるしな…」と両面を見てしまうことってありますよね。
それは優柔不断だからではなく、物事を一面的に判断しない“深い認知力”がある証拠なんです。
認知心理学では、HSPさんは「全体処理傾向(global processing)」が強く、相手の複雑な側面をまとめてとらえる傾向があると示されています(Aron & Aron, 1997)。

この力があるからこそ、人間関係がギスギスせず、あなたの周りには「話しやすい空気」が生まれるんですよ。
人を“完全に嫌う”のではなく、“受け止める”あなたの姿勢は、とても大きな価値があるんです。
あなたが悪いわけではなく、視野が広くてやさしいんですよ。
それは、これからもずっと大切にしていい資質なんです。

だから、「嫌えないこと=弱さ」ではないんだよ!
3.人間関係を育てる力になる
HSPさんは、人を嫌うより「なぜそうなったんだろう」と相手の背景を考える傾向があります。
その思考の深さがあるからこそ、対立を避けたり、場の空気を和らげたりできるんですよね。
例えば、トゲのある言葉を言われても、その裏にある事情を想像することで、怒りよりも理解に近づけることがあるんです。
心理学では、こうした態度を「寛容性(tolerance)」や「心の理論(theory of mind)」と呼び、他者理解の高さとして評価されます(Decety & Jackson, 2004)。

あなたが「嫌えない」のは、表面的な言葉や態度だけで人を判断していないからなんです。
その“受け取る力”が、実は周囲の安心感や信頼につながっているんですよ。
すぐに反応しないやさしさは、簡単にマネできるものではありません。
あなたの深さが、関係をそっと支えてくれているんです。

それは、立派な才能なんだよ!
4.守る方法をまだ学んでいないだけ
HSPさんは、優しさを持っている反面、その優しさを使いすぎると心が疲れてしまうことがあります。
でも、それは「あなたが悪い」からではなく、“優しさの扱い方”をこれから学んでいけばいいだけなんですよ。
例えば、
- 「苦手だけど、距離を取ってもいい」
- 「嫌ってはいないけど、関わらない選択もある」
といった視点を持つことで、心の疲労は軽くなっていきます。
心理学では「境界線(バウンダリー)」を引くことが、HSPさんにとって自己保護のカギになるとされています(Cloud & Townsend, 1992)。
あなたの優しさは、悪くも重すぎるわけでもなく、“バランスの取り方”を身につけるだけで心地よく保てるようになるんです。

疲れるのは優しすぎるからではなく、優しさの「出し方」にコツがあるということ!
まずは、自分を責めないでくださいね。
そのままのあなたに、やさしい生き方を重ねていけばいいんです。

優しさを守る方法は、ちゃんとあるよ!
5.人は安心していられる
HSPさんは、誰かを嫌うよりも
- 「受け入れよう」
- 「理解しよう」
とする姿勢を自然に持っています。
だからこそ、あなたと関わる人は「ここなら安心できる」と感じることが多いんですよ。
例えば、弱みを見せられたり、相談されたりする機会が多いのは、あなたが“否定しない空気”を出しているからなんです。
社会心理学でも、「非評価的な態度」は信頼形成に大きな影響を与えるとされており(Rogers, 1951)、HSPさんの穏やかな関わり方が人の心を守ることにつながっているんです。

あなたの“嫌えなさ”は、周囲にとって“安心の空気”に
それは、意識しなくても自然にできている、あなたのすごいところなんです。
だから、どうか「こんな自分でいいのかな」と思わないでくださいね。
「嫌えないあなた」は、たくさんの人の心に、やさしい灯りをともしているんですよ。

それは、誰にもマネできない価値だね!
“傷つかずに関わる”ための心のバリアづくり5選

“傷つかずに関わる”ための心のバリアづくり5選を紹介します。
- 何でも受け止めない
- 会話の中でちょっと距離を置く
- その場から離れる自由
- 相手の期待に応えすぎない
- 自分の心に余裕があるか
1つずつ見ていきましょう。
1.何でも受け止めない
HSPさんは、人の言葉や表情にとても敏感で、「それって私のせい?」とすぐに気を取られてしまうことがあります。
例えば、誰かが不機嫌そうにしていると、「自分の対応が悪かったのかも」と心の中で自問してしまうんですよね。
でも、他人の機嫌や反応すべてをあなたが受け止める必要はないんです。
心理学では「過剰な自己関連付け(personalization)」はストレスの原因になりやすいとされており(Beck, 1976)、HSPさんはこの傾向が強いといわれています。

だからこそ、「それは相手の課題かもしれない」と線引きする意識がとても大切なんです。
“感じ取る力”と“背負うかどうか”は別なんですよ。
「私が全部受け止めなくてもいい」と、心の中でつぶやいてみてくださいね。

そうすることで、優しさを保ちながら心を守ることができるようになるよ!
2.会話の中でちょっと距離を置く
HSPさんは、誰かの話を聞いているときに、その気持ちまで自分の中に取り込んでしまいやすい傾向があります。
例えば、相手の悩みに共感しすぎて、自分までつらくなってしまうことってありませんか?
そんなときは、
- 「今、話を聴いているだけ」
- 「相手の気持ちをすべて感じなくていい」
という心のスタンスが大切なんです。
心理学では「情動の境界線(emotional boundaries)」という考え方があり、相手の感情と自分の感情を切り分けるスキルが心の安定に効果的だとされています(Goleman, 1995)。
あなたが話を聞くときは、相手の気持ちを“全部”理解しようとしすぎなくてもいいんですよ。

「その人の感情」と「あなたの心」は別なんです。
一歩ひいて関わることで、やさしさを保ったまま自分を守れるようになります。
“共感”と“同化”は違うということを意識してみてくださいね。

それが、HSPさんのための心のバリアになるよ!
3.その場から離れる自由
HSPさんは、気まずくなりたくなくて、嫌な場面でもその場にとどまってしまうことがあります。
でも、「ここはちょっとしんどいかも」と思ったときに、その場を離れていいという“心の許可”があるだけで、ずいぶんラクになるんです。
例えば、会話がきつくなってきたときに「ちょっと飲み物取ってきます」と離れるのも、立派なセルフケアなんですよ。
心理学では「回避的対処(avoidant coping)」を否定的に捉えることもありますが、HSPさんにとっては“刺激から離れる”ことが回復に必要な対処とされています(Aron & Aron, 1997)。

つまり、自分を守るための“離れる選択”は悪いことではなく、むしろ必要なことなんです。
あなたが「ここは無理しなくていい」と思えるだけで、心はちゃんと守られていくんですよ。
いつでも抜けられる自由があるとわかると、それだけで緊張はやわらぐんです。
優しさを失わずに距離を取ること、それが心のバリアになるんですね。

“いつでも退室OK”の感覚を持っていてくださいね。
4.相手の期待に応えすぎない
HSPさんは、人から「頼りにされること」や「期待されること」に対して、つい全力で応えてしまう傾向があります。
でも、すべての期待に応えてしまうと、あなたのエネルギーはすぐに底をついてしまうんですよね。
例えば、誰かの愚痴を延々と聞いてあげたり、予定を合わせ続けてしまったり…。

そういったやさしさが積み重なると、気づかないうちに疲れやストレスとして表れてくるんです。
心理学では「自己犠牲的行動(self-sacrificing behavior)」はバーンアウト(燃え尽き症候群)の大きな要因になるとされています(Schaufeli et al., 1993)。
あなたのやさしさを長く保つには、“応えるライン”を決めることが大切なんですよ。
できることと、できないことを自分の中で整理してみてください。

あなたの限界を守ることは、相手との信頼を守ることでもあるんです。
やさしさは、無理をしなくてもちゃんと伝わります◎
5.自分の心に余裕があるか
HSPさんは、
- 「頼られたら応えなきゃ」
- 「助けたい」
と思うあまり、自分の余裕がないときでも力を出そうとしてしまいます。
でも、自分の心が満たされていない状態でやさしくしても、あとから疲労や後悔が押し寄せてしまうことが多いんです。
例えば、眠いのに相談に付き合ってしまったり、体調が悪いのに誰かの話を聞き続けたり…。

そういう時こそ、「今、私は大丈夫かな?」と一度立ち止まってみる習慣が大切なんです。
心理学では「自己調整能力(self-regulation)」が高い人ほど、ストレスに強いとされています(Baumeister & Vohs, 2004)。
つまり、“やさしくする前に、自分の状態をチェックする”ことが、心のバリアになるんですよ。
あなたの心に余裕があるときだけ、無理のない形で関わればいいんです。

やさしさは、まずあなたの心からあふれるものであってほしい
そのためには、あなたがあなた自身の味方であることが必要に◎
HSPのよくある質問

HSPのよくある質問をまとめました。
- HSPって理解されないの?
- 怒られると引きずる
- 人間関係で疲れる
- 仕事の人間関係で悩む
- 人間関係逃げていい?
1つずつ見ていきます。
HSPって理解されないの?
「HSPって理解されないですか?」という相談。

HSPといっても範囲が広いから、むずかしいよ!

具体的にどんなことが苦手なのか、どうしたらいいのかを伝えた方がプラスです◎
怒られると引きずる
「どうしても怒られると引きずってしまいます」という相談。

脳の特性がネガティブなことを思い出す傾向が強いんだよ

対策を6つ見ていきましょう!
人間関係で疲れる
「人間関係で疲れることが多いです」という相談。

そうだったんだね

疲れる原因と対処法を10解説しています。
仕事の人間関係で悩む
「仕事の人間関係で悩むことが多いです」という相談。

それはきついね

悩みが少しでも減らせるように下記記事で紹介しています。
人間関係逃げていい?
「人間関係で逃げるのはいいことですか?」という相談。

あなたの心の方が大事だよ!

あなたにとってプラスになる関係を大切にしてくださいね?
HSPの私・体験談

HSPの私・体験談を紹介します。
- 八方美人を卒業
- 苦手な人とは距離をとる
- 深入りしない
1つずつ解説します。
八方美人を卒業
以前は、だれからも好かれることが目標でかなり他人軸でした。
常に人の顔色を伺ってばかりだから疲れも半端なかったですね!笑
しかし、他人軸で生きても自分が笑えなかったら意味ないなって思って手放します。
苦手な人とは距離をとる
ていねいに接したらやはりマイナスな印象は持たれませんよね。
だから、個人的に合わないなと思った人がどんどん距離を縮めてこようとする時は、それ以上仲良くしないように話題を避けたりしてました。
物理的に近づかない、自分からは親しげにしないなど工夫がかなり必要でしたが、しっかり距離をとることを意識しています。
深入りしない
なんといってもこれかなと。
深入りするとかなりエネルギーが消耗することがわかったので、あえて浅く広くという関係を保っています。
これは個人差があると思うので、あなたが心地よいと感じる人付き合いを楽しんでいってくださいね◎

あなたの心が笑える素敵な関係を築いていってください!

これからも楽しんでいこう!










