
HSPさんにおすすめする本ってある?

あるよ◎600冊ほど読んできた読書愛好家の私がおすすめするよ!
前半では、HSPさんのおすすめ本を10冊紹介します。
後半では、自分を疲れにくくするための対策本を解説します◎
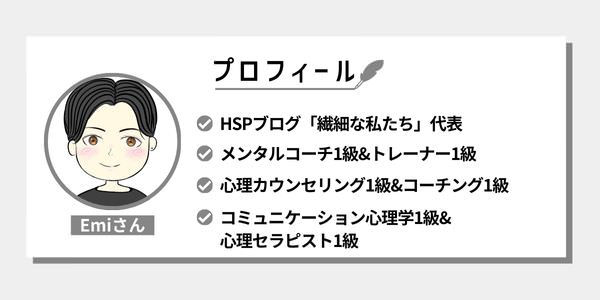
HSPさん向けのおすすめ本9冊

HSPさんにおすすめしたい本9冊を紹介します。
- 鈍感な世界に生きる敏感な人たち
- 繊細さんの本
- 「繊細さん」の幸せリスト
- 繊細な人をラクにする「悩み時間」の減らし方
- HSPの教科書
- HSPのためのハッピーアドバイス
- HSPサラリーマン
- まわりに気を使いすぎなあなたが自分のために生きられる本
- 「そのままの自分」を生きてみる
1冊ずつサラッと解説しますね!
1.鈍感な世界に生きる敏感な人たち

この本に出逢えてラッキーだなと心底思いました。

デンマークでHSPをカウンセリングした心理療法士さんのお話だよ!
著者のイルセさん自身がHSPであるということから、どのように疲れやすさと付き合っているのかを実体験を知ることができます。
また、HSPさんあるある「自尊心の低さ」をどのように癒していくのか、セラピーに訪れるHSPさんの共通点から学ぶことができました。
- HSPさんのギフト7つがわかる
- HSPさんが抱えやすい心の問題を知ることができる
- 非HSPさんと上手く付き合う方法がわかる
特に、非HSPさんとの関わり方は多くを学ぶことができました。
- 自分の限界点を周りの人に伝えること
- 深い話と表面的な会話を使い分ける
- HSPに理解がある人をパートナーにすること
また、敏感な自分とうまく付き合う方法をくわしく解説しているので、疲れやすさを軽減するヒントを得られます◎

あなたの気質を理解し、受け入れることができる素敵な本です◎
2.繊細さんの本

私がHSPであることを自覚できたきっかけの本です◎

多くの人におすすめられている本だよね!

繊細な気質を持っている600名以上のカウンセリングをされた方です。
著者の武田さんにカウンセリングを受けにきた繊細さんたちみんなが自分の長所に気づき、活かしはじめたことで人生が大きく変わったと言っています。
私たちと同じように、繊細さに悩んでいる人たちが肩の力を抜いて生きていける技術がここで解説されています◎
- 毎日のストレスを防ぐかんたんな技
- 肩の力を抜いてのびのび働く技術
- 繊細さんが自分を活かす技術
「繊細さんは、自分のままで生きることでどんどん元気になっていく」
繊細な自分を肯定し、自分にとっての
- 嬉しい
- 楽しい
- 心地いい
- ワクワク
をコンパスに、物事を選ぶことが自分らしさを大事にして生きるコツです。
我慢をやめて本音を大切にすることで「自分のすき」を大事にした生き方が選べるようになります。
私自身、「起業」というスタイルに落ち着いたのも
- 想い
- 得意
- 労働条件・環境
この3つが理想の状態だと感じたからです。
繊細さんが、自分の本音に正直に生きた時、これ以上にない自由を心から感じることができるようになります◎
3.「繊細さん」の幸せリスト

先ほどと同じHSP専門カウンセラーの武田さんが書かれた本です。

繊細さんがしあわせに感じられる53のコツが知れるね!
- 人生のときめきをアップさせる直感の使い方
- 感じる幸せを最大限受け止める方法
- やりたいことをやることで、周りの人を笑顔にする
「なにを感じても良いよ。大丈夫だよ」と繊細さと共に生きること。
それが、私たち自身の望みを叶えていくことに繋がっているのだと感じました。

一番深く感じたところは、「わかりあう」を手放すという考え方。

「わかってほしい」は相手に対するコントロールなんだよね
つい、自分の気持ちを共感してもらいたくて、相手に「わかってほしい」を押し付けていた部分があったなと反省しました。
「わかりあいたい」という思いが強いと、相手に振り回されたり、「どうしてわかってくれないの?」って歯痒い思いをした経験がこれまであったんです。
それからは、自分の考えや、やってほしいことを伝えるところまでが自分の領域だと、境界線をつける考え方を身につけることができました。
伝えたことに共感するかどうかは、相手の課題だと。

今では、課題の分離をすることができ、生きづらさがグンと減りました◎

自分にとってプラスになる考え方を取り入れるって大切だよね!
4.繊細な人をラクにする「悩み時間」の減らし方

精神科医の西脇先生が書かれた本です!

先生自身、アスペルガーを持っており、生きづらさの解決策を書くことに◎
HSPがどういったものか解説してくれる本はあっても、その悩みを解決するための本が少ないと思い、この本が生まれました。
HSPは心理学上の概念で、疾患ではないため治療の対象にはなりません。
それでもHSPさんは、生きづらさを抱えていることは事実です。
- 損する悩み
- 人間関係の悩み
- 生活の悩み
HSPさんは、想像力が豊かなのに、多くの人が損をする方向に使っているというところが刺さりました。
悪すぎる想像は、それ自体がストレスになるし、良い影響を与えてくれているとは言い難いですよね?
西脇先生もおすすめしている考え方に「憧れている人物」になりきるがあります。

自分の心の中に憧れの人を持つことで乗り切ることが◎
また、ネガティブな記憶がよみがえってきたら、それに適当に名前をつけるというのもおもしろいなと。
- ぴろぴろ
- てんてこ
このように、適当に名前をつけることで、気持ちの整理をつけることができます。
名前をつけることで、頭の中に「置き場所」ができ、気持ちを落ち着けることに◎

今からやってみよう!っと♪
5.HSPの教科書

HSPの良さを伝えている活動家として知られています。

4人のお子さんがいらっしゃるんだよね!
- 置かれた状況をプラスに捉え直す考え方を知れる
- 日常の優先順位の決め方
- HSPのパートナーシップ
HSPさんは、ネガティブなことが見えるとそこに意識を向けてしまいがち。
そんな時に使える「リフレーミング」という考え方ができるようになったら、あなたの強みを活かした場所や環境で生活できるようになります。
リフレーミングの2つの基本。
①状況のリフレーミング
気質自体を変えるのではなく、その気質を活かせる状況に身を置こうということ。
②意味のリフレーミング
今起こっているこの事には他にどんなプラス要素があるのか?どんな良い事があるのか?
本書では、HSPさんのあるあるのマイナスな考え方を前向きに捉え直すことができるワード集を紹介してくれています。
ぜひ、マイナスな部分で止めるのではなく、あなたの可能性に目を向ける捉え方をしてほしいなと思います。
HSPさんが陥りがちな思考に気づくことで、どのように対策を打てば良いのかが見えてきます◎

自分の思考のクセを知るって大切だよね!

無意識の思考パターンを知る事で、どう捉えていきたいかに目を向けられるよ◎
6.HSPのためのハッピーアドバイス

精神科医の明橋先生が書かれた本です。

繊細さを持っている自分を肯定できる本だね!
怒りという感情には、悲しみや寂しさが隠れているということ。
感情の深層心理についても深掘りされていて、気づきをたくさん発見しました。
- 繊細さん✖️非HSPさんの人間関係
- 親密さへの恐れ
- 自分の愛着スタイルの型
上記の5冊では触れられていない部分が多く、精神によりフォーカスした内容でした。
友達や恋人の価値観はみなそれぞれ違います。
だからこそ、相手の気持ちや考えを尊重する受け答えを心がけていきたいなと思いました。

だれかとの親密さへの恐れは、幼児期か成人かという点も刺さります。
「〇〇したいのに、〇〇できない」という行動の足枷はこれまでの経験で傷ついた経験があるから。
考え方を再度捉え直すことも大切ですが、自分の過去に起きた出来事の感情を癒す必要性も学ぶことができました◎
私自身、心理セラピストや心理カウンセラーの勉強を現在もしていますが、もっと深掘りしていきたいと思いました。

繊細さは幸せを最大限受け止めるためにある!

あなたの繊細さは、あなたを幸せにしてくれます◎
7.HSPサラリーマン

起業家であり、個人事業主を育てる経営スクールの運営をしている春明さんの本。

営業成績で思うような結果が出なかったけど、ついにNo.1になるまでの話。
お金を得るだけではなくて、お客さまにどうなってもらいたいのか、彼の視点が徐々に「相手」目線に変わっていきます。
彼をここまで成長させてくれるたった1人の先輩と、友人との出逢い。
「人を嫌いだ」と思ったいた彼が、「早く人に会いたい、幸せにしたい」と思えた時、周りの人・お客様の笑顔の輪がどんどん広がってきます。

物語形式で読みやすいです。

何度も号泣しちゃった
- 言葉で人生が前向きに変わること
- どう受け取るかで生き方が変化すること
- 人を幸せにすることが成幸だということ
仕事でうまくいかない、なんかマイナスな気持ちに今なってるな、そんな時にあなたを支えてくれる言葉に出逢います。
誰と会いたいか?どんな時間を過ごしたいか?どういう姿を見たいか?
引用:「HSPサラリーマン」p.170
周りが自分を見捨てることなんてない。真っ先に、いつも自分が自分を諦める。
引用:「HSPサラリーマン」p.206
大事なのは、「どれだけがんばるか?じゃなくて、どれだけ幸せにするか?」なんだよね。
引用:「HSPサラリーマン」p.277

心動かされる言葉にたくさん出逢えました!

お守りの言葉に出逢えるよ
8.まわりに気を使いすぎなあなたが自分のために生きられる本

HSP専門アドバイザーとして活躍されているRyotaさんが書かれた本です!

Ryotaさん自身もHSPさんなんだよね!
- HSPさんの性格傾向
- 自分を助けるには自分を認めることから
- HSPさんの悩みを解く6つのカギ
Ryotaさん自身の気質や、現在の職を選ぶまでにたくさんの壁があったと本書で語っています。
彼がどの章でも必ず押さえているポイントに、他人の評価を気にしていないか?が挙げられます◎
上記で挙げられた本の中で触れられていない箇所を、本書で見つけることができました。

「甘え」について教えて
幼少期に反抗期がないと、自分の甘えを相手にぶつけたり、自分の意見を伝えることが困難になるといわれています。
その結果、人から指示されたり、干渉されることで我慢が限界に達すると、人が変わったように怒りを爆発させてしまうことも。
甘えを我慢しすぎると、物事を否定的に捉えがちになります。
そうすうと問題がどんどん大きくなり、つらくなってしまいます。

甘えを我慢しすぎてつらくなっているときは、気持ちを吐き出すことが必要です。

自分の本心を伝えるんだね
プライドが邪魔をすることも、もしかしたらあるかもしれませんが、自分の気持ちに嘘はつかないでください。
あなたがあなたの甘えに気づくことで、自分で甘えを満たすことができるようになります◎

巻末特典に、HSP診断があります◎
9.「そのままの自分」を生きてみる

精神科医の藤野先生が書かれた本です。

弱くてポンコツな自分もかわいいよね
「変わりたい」という思いには2つあるといいます。
- 自己否定からくる変わりたい
- もっとよくなってもいいかな?前向きの変わりたい
無理して自己否定からくる変わりたいは、自分を歪ませてしまうことになるかもしれない、と。
他人を目指した先に理想の自分はいないんです。
だから、変わる前に「自分の心のケアを先にしてね!エネルギーを貯めてね」と呼びかけています。
- 自分を大切にすることの大切さ
- 「自分を変えたい」という気持ちを手放す
- 他人の言葉を真に受けない
「自分を変える」ってパワーがいります。
だって、多かれ少なかれ、これまで生きてきた自分の人生を「否定することになる」から。
- 今の自分ではダメな気がする
- こんな状況のままでいいの?
あやふやな感じを、「変わりたい」に変換している。
それって、「これまでやってきたこと、今までの生き方を含めた、今の自分を否定すること」でもあるんです。
自分を否定する方からくる「変わりたい」ではなくて、
- 「今の自分もすきだけど、次はこういう自分も面白いかも」
- 「こうなったら可能性が広がるかも」
このように前向きになった時に、自分の中の「変わりたい」を採用してあげてもいい。
それがまだなにかはっきりしないのなら、「私、変わりたいんだな」くらいの気持ちの受け止め方で、自分をいたわる方を優先させてあげてください◎

あなた自身があなたのいちばんの味方でいてほしい
疲れやすさを対策する本10冊
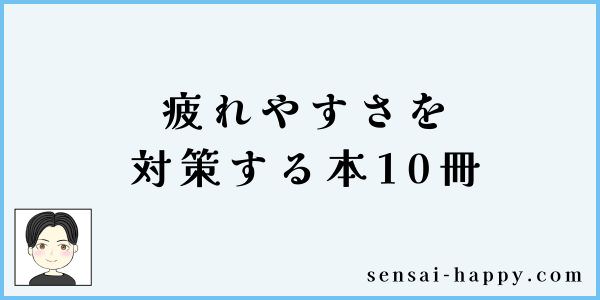
疲れやすさを対策する本10冊を紹介します。
- 嫌われる勇気
- 手放す練習
- ストレスを操るメンタル強化術
- 自分を育てる方法
- 言語化の魔力
- 人生を思い通りに操る 片付けの心理法則
- 直観力
- 究極のマインドフルネス
- 後悔しない超選択術
- 無(最高の状態)
1冊ずつ解説していきますね!
1.嫌われる勇気

人に嫌われてもいい、そう思えたのはこの本を読み終わってからでした。
欧米で絶大な支持を誇る「アドラー心理学」について学びたくて、手に取りました。
- どうすれば幸せに生きることができるのかのヒントを知れる
- 自分がコントロールできない範囲がわかる
- アドラー心理学(勇気の心理学)が、「人間理解の真理、到達点」として受け入れられる理由を理解できる
いかなる経験も、それ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない。
われわれは自分の経験によるショック、いわゆるトラウマに苦しむのではなく、経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。
自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである。
引用「嫌われる勇気」p.29

人生とは誰かに与えられるのではなく、自ら選び取ることなのだとアドラーはいいます。

今、この瞬間から選び取れるってことだよね!
答えとは、誰かに教えてもらうのではなく、自らの手で導き出していくべきもの。
引用「嫌われる勇気」p.40

だれかから与えられた答えは、しょせん対症療法でしかなく、価値がないものと考えられています。

最後は自分が選ぶんだ
気質や性格は、自分の意思とは無関係に備わっているものという考え方が一般的。
アドラー心理学では、ライフスタイルは自分で選びとるものだと考えている。
人はいつでも、どんな環境に置かれていても変わることができる。
引用「嫌われる勇気」p.49
後天的に自分で選びなおすことができるのだと伝えています。
それでも、ライフスタイルを変えないのは、「自分自身が変わらない決心をくり返している」からだと。
客観的な事実を動かすことはできないが、主観的な解釈はいくらでも動かすことができます。
ライフスタイルを変える「勇気」を自分自身の中で育てる必要があるんです◎
2.手放す練習
HSPさんはモノからくる刺激にも敏感だと知り、少しでも刺激を減らしたくてこの本を手に取りました。
読んで、できそうなところから1つずつ実践。
なんとなくではなく、心からお気に入りのモノだけに囲まれることで以前よりも大切にモノを扱えるようになりました◎

おかげで大切なモノに時間を使える生活を送れています。

もう前の生活に戻れないね!
年齢を重ねれば重ねるほど、物を捨てづらくなるというデータがあります。
自分にとって「何が必要で、何がいらないのか」を早い段階で見極められるようになりたいあなたにおすすめです。
- モノを減らせば幸せになれる理由を学べる
- モノを上手に減らせる工夫を知れる
- 減らすことで自分の好きに出逢える
背負うカバンが重くなるほど意思力が奪われて、無駄遣いが増えるという研究結果があります。
カバンの中に入っているモノを、本当に必要なものだけ入れることで、ストレスフリーを叶えることができます♪
モノへの執着を減らすことで、仕事や人間関係もうまくいくようになります。

私たちが一日のうち浴びている情報量は江戸時代の一年分といわれています。
情報過多、モノも過剰に溢れている現代だからこそ、持ち物を少数精鋭に絞ることで、悩むことが減っていきます。
「写真に撮ってから捨てる(思い出のダウンサイジング)」という方法は、不要品を「写真に撮ると15%も多くモノを減らせる」というペンシルベニア州立大学の実験結果で分かった。
引用「手放す練習」p.192
本書からたくさんの驚きを知り、生活をコンパクトに変えることができました!
ぜひモノ疲れから解放されたい方に、手に取ってほしい一冊です。
3.ストレスを操るメンタル強化術

ストレスを軽くしたり、エネルギーに変えるための方法が知りたいと思ったから手に取りました。
- メンタルを強くするために何が必要かわかる
- ストレスを軽くする方法を知れる
- ストレスをエネルギーに変える方法が学べる
ラトガース大学では、氷水に手を入れて一定時間我慢してもらうというストレス実験をした。その結果、氷水に手を突っ込む前に、楽しい記憶をたった14秒間思い出すだけでストレスに強くなることがわかった。
引用「ストレスを操るメンタル強化術」p.40
スマホの待ち受け画像を、自分の大事な想い出や楽しかった時の写真にしておくことで、見るたびに癒されます。

楽しい記憶ってすごい!
- 何かに挑戦する時には同時進行でその一部始終を記録に残す
- 失敗を成功モデルに変えるためにも、どう乗り越え、解決したかまで記録する
人間は過去を正確に思い出すことが苦手な生き物で、時間が経つと改変されることもあります。
だからこそ、記憶に頼らずに記録をとることが必要になります。
そうすると、自分の失敗パターンを把握したり、問題解決する時間に充てることができます!

「失敗はこわいものだ」という認識ではなく、成長させてくれるもの◎

ブレないメンタルを作りたいあなたにおすすめ!
4.自分を育てる方法

コーチをされている中竹先生の本です。
- 自分で自分を育てる力(セルフリード)を身につけれる
- 自分の意志で、自分のペースをコントロールすることができる
- 柔軟でしなやかな生き方をするヒントを得られる
セルフリードとは、自分で自分を育てる力。
与えられた目標をこなすだけの自分を卒業して、目標を自ら見つけ、定め、自分を進めていく。
自分自身がどんな人間で、何が好きで、何を得意としているのか。
偏りのない目線で見つめながら、ありのままの飾らない自分で無理なく楽しく力を発揮できる状態をキープしていく。
「自分を育てる方法」p.13
主体的に自分と向き合い、自分の人生を小説の主人公として生き抜くために身につけたい力です。
強みは弱みであり、弱みは強みである。この相互の行き来を、脳内で瞬時に転換できるようになることを強くすすめたい。
「自分を育てる方法」p.53
結婚生活を共にしてきたパートナーから「あなたは人に依存している」と言われ、大きなショックを受ける。
セルフリードを学べる会に参加し、初めて自分自身の内面に向き合う。
「これまで自分の言葉を使って、自分の気持ちをほとんど言ってこなかった」
「人の話を聞いているようで、本当に聞こうとしていなかった」という反省点に気づくことができた。
それから、パートナーに対しても「なぜそう思うのか?」と質問する勇気を持てたり、相手の本心を理解しようと努力できる自分に変われた。
パートナーとも復縁でき、2人での生活を再開できた。
「自分を育てる方法」p.14
この女性は、現在の自分を認め・振り返り、自分の生き方を少しずつ変えていきました。
ネガティブだった思考がポジティブに変わることで以前よりも自分に自信を持つ事ができ、パートナーとの関係も良好だというエピソード励まされます!

気分が落ち込んだ日は、自分の弱みを強みの表現に変えてニュートラルな感覚を身につけていきたいです。
「自分の可能性を広げ、もっと会社や世の中に役立って喜ばれる存在でありたい」
そう願うあなたにぜひ手に取ってほしい、本。
5.言語化の魔力

精神科医の樺沢先生が書かれた本です。
- 悩んでいる人の脳内で何が起きているのか知ることができる
- 悩みが起きた時の対処法について理解することができる
- ネガティブなことよりも、ポジティブなことに注目できる方法を知れる
考えたくもないのに、グルグルと悩みが浮かんでは消えを繰り返している。
どうしてそのようなことが起きるのでしょうか。
理由は、脳の作業領域(ワーキングメモリー)が3つしかないから。
どんなにがんばって覚えようとしても、頭の中にはトレイが3つだけ。
だから、一度にすべてのことを処理するのは脳の特性上、不可能なんです!
スウェーデンの心理学者ロバート・カラセックは、
- どんな仕事がストレスになるのか
- どうすれば職場のストレスを減らせるのか
を研究し、結果をまとめました。
同じ仕事を、同じ時間していてもコントロールできているという感覚があれば、ストレスは減り気分は楽になる。
引用「言語化の魔力」p.48
0か100かで物事を決めたり、見たりするのは後々自分を追い込むことになります。
悩みがあるのなら、どれくらいコントロールできるか数字(0〜100まで)で考えます。

コントロール率0%なら諦める

コントロール可能率が高めなら、徐々に上げていく
この2点を押さえることで、悩みを少しずつ解消することができるようになります。
6.人生を思い通りに操る 片付けの心理法則

科学的視点から片付けるメリットについて知ることができます。
「捨てたいけど、必要かも」
捨てるには微妙なラインのモノ、ありませんか?
そんな時どうすればいいんでしょうか?
迷わずに捨て、モノが勝手に減っていく有効な7つの質問があります。
- 一旦捨てたとして、これを買い直すか?
- 長期旅行に持って行きたいモノか?
- 誰かが買ってくれるとしたら売るか?
- あの日に戻れたとして、やはりこれを買うか?
- お金が無限にあったら、本当にこれを買うか?
- これを何回我慢すれば、ほしいモノが買えるか?
- 3年、5年、10年経っても必要か?
わたしも一時期、モノを減らしたのに増えていた期間があり、モノを増やす時どんなルールに従えばいいのかの答えが知りたかった時期があります。
減らしたら、増えないようにマイルールを守ることがミニマル生活を楽しむ醍醐味ともいえます。
モノに持たれるのではなく、生活を豊かにしてくれるモノを持つという感覚を育みたいあなたに、おすすめの本。
7.直観力

メンタリストDaiGoさんが書かれた本です!
人生は選択と決断の繰り返しです。
だからこそ、「あの時こうしておけばよかった…」という後悔を減らせるようにと思い手に取りました。
- 自分が進みたい道を間違えずに選択できる方法を学べる
- 直観を高める習慣が分かる
直観とは、人生における選択と決断の最大のよりどころとなる能力。
引用「直観力」p.3
直観力は無意識に生まれる判断や評価のことを指します。
反対にバイアス(偏見)とは、生まれた先入観や思い込みで偏りが生じることを指します。
偏った見方で物事を見ると、直観力が本領発揮されないままになります。

軽いジョギングやウォーキングなどの有酸素運動を行うことを推奨されています。
理由は、有酸素運動をすることによって脳の中に脳由来神経栄養因子(BDNF)という物質が分泌されるから。
イリノイ大学のアーサー・クレマンの研究では、定期的な散歩によって意思決定を司る前頭葉の機能が活性化するという報告が出ている。
ハーバード大学のジョン・J・レイティ博士の研究でも、10〜20分くらいの早起きで、脳が成長することが分かっている。
引用「直観力」p.202
早歩きすることで頭が冴えて創造性が高まり、その効果が持続することが研究結果によって証明されています。

毎日朝散歩をしているよ!
日立製作所でAI(人工知能)開発に携わっているチームによる研究では、人の主観的な幸福感はクリエイティブなパフォーマンスに大きく影響することが分っている。
幸福感を持っている人は、そうでない人に比べて3倍もクリエイティブになり、仕事の生産性が37%も高くなる。
年収が高く、昇進も早い。
プライベートも充実し、心身ともに健康で寿命も長いなど受けるメリットが多い。
引用「直観力」p.100
自分がどんな時に幸せを感じるのか、そのために何をすべきかを考えて行動すると直観力がアップします◎

上記の研究結果から、自分を客観視するのが重要ということがわかりますね◎
直観力のある人の共通点として、直観を行動に移しても「あれ?なんかちょっと違う」と違和感を感じたら「すぐに軌道修正する」が挙げられます。
「悩む前に動く」
動きながら答え合わせをしていきたいと思いました◎
8.究極のマインドフルネス

不安感が強い私が行動できるようになったきっかけの本です。
- 今日から試せる「不安感を減らす」習慣を知ることができる
- ストレスをプラスに捉えることで得られるメリットについて理解できる
- 悩みすぎる性格は自分にとって強みであるという新たな視点を持つことができる
不安感を減らせる習慣がいくつも紹介されています。
2015年にアメリカのスタンフォード大学が、反芻思考が起こりやすい人たちの脳をスキャンしながらチェックする研究を行った。その結果、「森など木がたくさんあるところを歩くだけでも反芻思考が止まり、うつ病の改善につながる」ことがわかった。
引用「究極のマインドフルネス」p.23
クヨクヨ悩みすぎてしまう思考の回数が自然の中を歩くことで減るというのが素晴らしいです。

観葉植物を得られるメリットもあります!
- 疲労や頭痛の改善
- 肌の乾燥の改善
- 創造性が15%アップする
- 病気にかかる確率が減る
「ポトスは育てるのが楽で、有害物質を吸収してくれる非常にすぐれた植物であることをNASA(アメリカ航空宇宙局)も認めている。」
引用「究極のマインドフルネス」p.24
ダイソーにもポトスが置かれていたので、お手軽な観葉植物ですね!
メンタリストDaiGoが定義している「自信」についても響いたので共有させていただきます。
自分の将来、人間関係など、自分の世界を自分の力で変えることができるという信念のこと。
自分はここまでなら叶えられそうだという目標を実現できることを指します。
自分の目指している理想の体を目指して筋トレをし、狙った通りに変えられると「自分はできる!!」に変わります。
筋トレだけに限らず、仕事やプライベートにもプラスの連鎖が起き、「こうしたい!」を「叶えられた!」にすることができます。
引用「究極のマインドフルネス」p.71
「自分を変えよう、自分の弱点を変えよう」と思えば思うほど、不安やうつが悪化していく。
一方で、「他人のために何かをしよう」と思うだけで、不安とうつの症状が改善し、人間関係のトラブルを起こしにくくなった。
引用「究極のマインドフルネス」p.78
目標の立て方は2つあります。
「自己」なのか、「他者」なのか。
この研究は、実験を受けた当事者だけでなく、家族や友達など第三者から見ても、メンタルが安定して見えたり、人間関係が良好だと判断されています。
今やってることが大切な人たちの力になると思うことで、メンタルがいい方向へと変化し、人間関係も良くなるって素敵ですね。

「幸せにしたい人のために」が私たちのメンタルを支えてくれるんです。
9.後悔しない超選択術

あらゆる選択においてベターを見抜く力を養いたいと思い取った本です。
後悔しないための選択を身につけるために、今日から何ができるのかという点に焦点を当てています。
心理学、脳科学の実験では、「正しい選択はない」という衝撃的な結果が出ました。
後悔しない選択を目指すためには、自分の意思決定スタイルを知ることが重要だといわれています。
合計で5つ。
- 合理的スタイル:条件が揃っていればブレずに選択する。
- 直感的スタイル:ピンときた!という、自分の感覚を重視するタイプ。
- 依存的スタイル:他人のアドバイスに耳を傾け、意思決定していく。
- 回避的スタイル:最終決定を先延ばしにするタイプ。
- 自発的スタイル:選択するスピードが速く、決断力があるタイプ。
意思決定において、下した選択とその結果について後悔していない確率が最も少なかったのが、合理的スタイルでした。
決断を下すのに時間はかかるという難点がありながらも、判断材料を丁寧に分析した上で選択しているからだとのこと。
直感タイプのように、感情に囚われて決断することを避けるためにも、「長期的に考えること」を薦められています。

意思決定の前に1年後、10年後の結果を想像することが大切です。

その癖をつけると、一時的な感情に惑わされなくなるね!
他にも、過去の経験、失敗から学んだら記録をつけるなど、即実践できるテクニックが紹介されています。
自分にとってプラスな選択ができるようにするために、これからも読書をして、軌道修正していきたいです!
後悔を最小限に留めたいあなたに読んでほしい、本。
10.無(最高の状態)

私の憧れ、サイエンスライターの鈴木さんが書かれた本です。
人類はみな「生まれつきネガティヴ」である、と序章の言葉に心を掴まれました。
人間はポジティブな情報よりもネガティヴな情報の影響を受けやすく、マイナスなことほど記憶に残るという心理があります。
私たちの苦しみは、「不足を知らせる」メッセンジャーとして機能しているといえます。

例えば、「怒り」は、自分にとって重要な境界が破れたことを知らせています。

「嫉妬」という感情は、重要な資源を他人が持っていることを教えてくれているんだ!
このように、日々感じている感情を紐解くと、自分が今何を求めているのかに気づく事ができます。
おもしろいなぁと感じたのは、p.60の「ヒトの脳は0.1秒でストーリーを生み出す」という箇所。
現在の神経科学では、ヒトの脳は物語の製造機だとも。
私たちは脳が作り出したシュミレーション世界を生きていて、日常の活動に使うリソースを節約するために行われているんです。

危機を逃れるために、脳が物語を作っていることが理解できます!
600冊読んだおすすめ本No.1
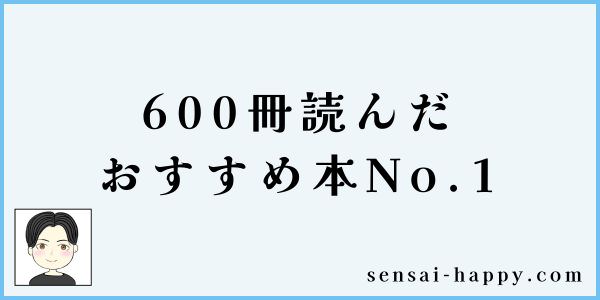
「運転者」

「運転手」ではなく、「運転者」という表記にドキッとしたんです。
- 不機嫌でいることよりも上機嫌でいることの大切さを学べる
- 自分の運は自分の物事への反応で変わることを擬似体験できる
- 何歳からでも人は変わることができるという感動を味わうことができる
「運は〈いい〉か〈悪い〉で表現するものじゃないんですよ。
〈使う〉〈貯める〉で表現するものなんです。
だから先に〈貯める〉があって、ある程度貯まったら〈使う〉ができる。
少し貯めてすぐ使う人もいれば、大きく貯めてから大きく使う人もいる。
どちらにしても周囲から〈運がいい〉と思われている人は、貯まったから使っただけです。」
引用「運転者」p.65
貯めることをせず、いいことが起きないかと考えがちです。
「基本姿勢が不機嫌な人に、毎日の人生で起こる幸せの種を見つけることなんてできない。」
引用「運転者」p.93
上機嫌でいることで物事がいい方向に進む確率がグンと高まることを本書のストーリーを通して実感することができました。
歳を重ねても「自分の機嫌を自分で取ること」が、どれほど重要なのかがが分かるストーリーになっています。

今日が一番若い日だよね!

どう捉えるかはいつだって選べます◎


